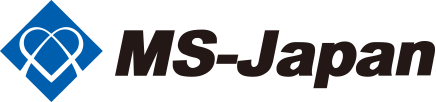お役立ち資料・コラムUSEFUL DATA/COLUMN
バックオフィス部門の中でも、法務部門は決まったルーティーンワークの比率が少ない部門の一つで、スタッフ一人ひとりの仕事を一定期間で区切って評価するのは難しい傾向にあります。 特に、M&A・戦略提携のようなハードルの高い案件は、枠組みを設けて仕事内容を評価しにくいという難点があり、定量評価を取り入れにくい特徴を持っています。
法務の目標設定を行うには、このような課題を理解した上で、法務独自の観点から目標を把握する必要があります。 この記事では、法務の目標設定における課題と、具体的な目標設定例についてお伝えします。
法務の目標設定の課題
冒頭でお伝えした通り、法務というセクションのルーティーンワークは、他のバックオフィス部門と比べて少なめです。 そのため、目標設定の際に以下のような課題が生じてきます。
具体的な数値目標が立てにくい
法務部門は、あらかじめ定められた職務が多数あるわけではなく、あったとしてもごく一部です。 業務の大半は部外から舞い込んでくるもので、その都度異なるミッションに対応しなければならず、定量評価を行えるほど膨大なケースの蓄積があるわけではありません。 よって、どの案件をどのように処理したのか・それが会社にとって後々どのような利益をもたらすのか、判断するのが難しいのです。
法務が一人体制の企業も多い
ベンチャー企業では、総務担当者が法務を兼任するなど、一人体制で法務というセクションを回していかなければならないことも珍しくありません。 評価対象が一人しかおらず、内情を知っているスタッフがほとんどいない中では、経営者に評価をゆだねるのはむしろ自然な流れに感じられます。 ただ、将来的に部下を持つようになることを想定して、自分が評価を下す立場に立つことも踏まえつつ、やはり目標設定の準備はしておくべきでしょう。
減点主義になりやすい
法務の評価は、客観的な評価基準を作りにくい分、どうしても定性評価の割合が高くなり、スタッフの評価が減点主義になりがちです。 一つひとつの業務の難易度は、法務の場合は一概に表せるものではないため、数値で表現できない要素の評価に偏ってしまうおそれがあります。
法務の目標を定量化する方法
会社の数字そのものに深く関係しているセクションではない法務は、そもそも目標を定量化しようとすること自体がナンセンスだと言われることがあります。 事実、定量化しようにもルーティーンワークや比較要素が他の部署に比べて少ないわけですから、検討するだけの材料を集めることは難しいかもしれません。
しかし、総合評価を前提として、一部業務の定量評価を行うケースも見られます。 契約審査・紛争処理のスピード・件数を材料にすれば、誰が早くて確実なのかを見定める要素として使えるでしょう。
社内業務で考えれば、社員向けの研修実施回数・担当回数を評価基準に含めてもよいですし、その後の研修評価で一定の数値を記録することをノルマにする方法もあります。 サンクスカードを活用することを考えるのであれば、他部門のフォローに対する評価を判断する指標として、もらった枚数を利用してもよいでしょう。
どんな会社の法務部門においても、定量化できる要素は必ず見つかります。 ただし、それはあくまでも評価の一部として捉え、基本的には数字にかかわらず社員の能力・適性・実績を判断することが大切です。
法務の3つの評価基準
突発的に案件が増えていく法務では、目標や評価基準を設けたとしても、その達成に向けて事を進めるのは至難の業です。 それを踏まえた上で評価基準を構築するのであれば、以下の3つの視点が参考になるはずです。
1.ほぼ日次業務にカウントされるものを評価する
比較的難易度が低く、スタッフの多くが対応できるものについては、定量評価を行う方向性で考えてみましょう。 例えば、リーガルチェックや研修に関することが該当します。 これらは、正確性や回数・処理速度に応じてある程度は数値化できることから、基礎能力の評価として使えます。
2.新しい仕組みの導入・既存業務サイクルの改善に向けた動きを評価する
日々の業務の中で、新しいサービスを導入して作業効率化を図る・既存の業務サイクルを改善する方法を探る機会は、一般社員にはなかなか巡ってきません。 それをあえて、数多くの実務に携わる社員たちに任せることで仕組みを変えるという視点は、評価の面でも事業運営の面でも大きなメリットになります。 評価基準については、提案回数や稟議が通った数・影響の範囲や効果などを考慮して判断します。
3.突発的な案件の難易度に応じて評価する
法務に回ってくる案件の内容は、残念ながら法務自身で選ぶことはできません。 また、話が来た時点でかなりひっ迫した状況になっているケースも多いことから、そのような事情を勘案した上で仕事の精度を評価していくという方法もあります。 担当者がどれだけ主体的に物事を進めてきたのか・今まで誰もやったことがなかった案件なのかなど、複数の観点から定性評価を試みます。
法務の目標設定例
先の3つの視点を踏まえ、続いては法務の具体的な目標設定例についてお伝えします。 各社の実情に応じて、どのようなものが参考になるかは変わってきますが、以下のいずれかが役に立つはずです。
日次業務の目標設定例
日次業務に関しては、まず定量化ができる業務がどのくらいあるのかを把握します。 また、それらの業務は単独でできるものか、複数人が担当するものなのかを区分します。
その上で、仕事の数量に応じた目標を割り振り、一定の数値以上に達したかどうかで評価できるようにします。 具体的には、契約書の審査件数・法律相談を実施した件数など、数値化できるものをベースにして目標を設定し、他に設定した目標の達成状況と合わせて総合評価の材料とします。
業務改善の目標設定例
業務改善の目標設定は、最初の段階ではスタッフ自身の身の回りにある問題を認識させ、それを改善するためにどうすればよいのかアイデアを出すところから始まります。 そこで、問題に対して実際にアイデアを実行に移せたのか、その結果誰がどのくらい影響を受けたのか、改善案がもたらしたインパクトはどのくらいの大きさだったのかなど、複数の観点から評価できるようにします。
突発案件の目標設定例
突発的に発生した案件の対応については、評価そのものが難しく、成功したかどうかは後にならなければ分からないケースも数多く存在します。 それを踏まえた上で、各案件で必要な手続きを滞りなく進められたかどうか・前例がない新しい挑戦かどうかなど、総合的な難易度を評価できるようにします。
360度評価を活用する
「法務の仕事を定量化するのが難しい」という観点から、360度評価に興味を持つ法務スタッフもいます。 360度評価とは、一人の社員をあらゆる角度から評価する方法で、上司・同僚・部下・他部門の関係者から多面的な評価を得るために用いられます。
360度評価を導入している企業は多いものの、運用上は人材育成・組織活性化を目的として用いられるケースが多く、人事評価で用いられた例は聞かれません。 また、評価する側の評価スキル・評価対象に対して抱いている印象など、本来なら評価者にふさわしくないファクターを持つ社員が実際の評価に携わってしまうリスクもあります。
しかし、法務部門という一つの狭い世界から社員を解き放ち、部門の人間が把握していなかった問題点を明らかにする点では、今後の成長に関連した重要な情報が見つかる可能性があります。
法務スタッフ側が気を回してやっていたことが、実は他部署では二度手間を招いているなど、実情を知らないことで続いている悪い習慣は、どの会社にも往々として存在しています。
360度評価は、単純に上司・部下・同僚の関係性だけで利用するのではなく、部外者の目から見た評価を反映させるのに活用することが大切です。
まとめ
法務部門の目標設定は、ある意味「課題を見つけること自体がナンセンス」だと捉えられがちです。 それだけ多方面から仕事を依頼される部門ではあるものの、いつまでもそのような考えに逃げていると、組織として・個人としての成長を放棄していることになります。
確かに、法務含めバックオフィス部門の目標設定は難しいものがあり、自社にあった事例を探し出すのも一苦労です。
また、せっかく事例を見つけたとしても、当の社員たちが提案に反対するおそれもあります。
しかし、法務の存在意義を見据えた時、法務という職種が客観的にどのくらい会社に貢献しているのかを説明できなければ、将来的に任を解かれてしまうリスクは十分考えられます。
難しいですが、決して事例がないわけではないので、少しずつ自社に合致するような目標の設定方法を探っていきましょう。
【この記事を読んだ方におすすめ】
>人事評価における目標設定のポイント。管理部門の目標設定例など
>目標設定に活用できるフレームワーク7選
-

-

お電話での
お問い合わせ- 東京本社
03-3239-7373
- 横浜支社
045-287-8080
- 名古屋支社
052-551-1125
- 大阪支社
06-6292-5838