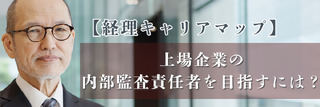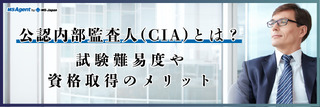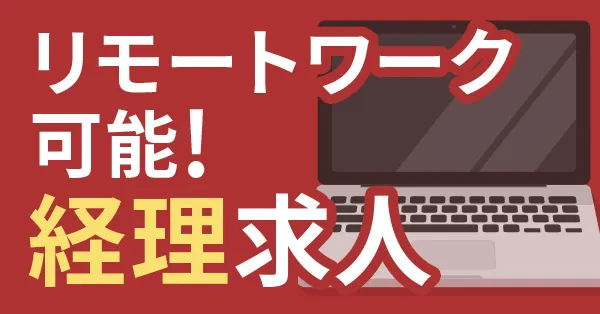【内部統制・内部監査・内部統制監査】各言葉の意味や注目されている背景を解説!



内部統制や内部監査という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。
ビジネスに関わる人なら知っておきたい言葉です。
この記事では、内部統制部門への転職を検討している方向けに、内部統制・内部監査の違いや役割について解説し、内部監査に必要なスキルや経験なども紹介しています。
内部統制や内部監査について気になる方は、参考にしてみてください。
内部統制、内部監査とは何か?
内部統制とは
内部統制とは、会社が健全に事業活動を遂行するためのルールや仕組みのことです。
たとえば、書類の不備を防ぐためのダブルチェックなどの仕組みが挙げられます。
内部統制の目的は、財務報告の信頼性を確保し、法令遵守を促進することです。
内部統制の4つの目的と6つの要素
内部統制を理解するためには、4つの目的と6つの要素を理解しておくことが肝心です。
まずは目的をチェックしましょう。
- ①業務の有効性及び効率性:事業活動の目的の達成のため、業務の有効性及び効率性を高めること
- ②財務報告の信頼性:財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保すること
- ③事業活動に関わる法令等の遵守:事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進すること
- ④資産の保全:資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行われるよう、資産の保全を図ること
内部統制の要素は以下の6つです。
- ・統制環境:組織の文化や構造、リーダーシップなど、統制を支える基本環境
- ・リスクの評価と対応:リスクを特定し、それに対応する方法
- ・統制活動:リスクを管理するための具体的なポリシーと手順
- ・情報と伝達:関連情報を適切に収集し、共有すること
- ・モニタリング:統制システムの効果を定期的に監視し、必要に応じて改善すること
- ・ITへの対応:情報技術を利用して統制活動を支援すること
内部統制は、とくに財務報告に関連して重要視され、経理や財務の専門知識や法律知識など幅広いものが求められます。
昨今、日本企業の不祥事が相次ぐなかで、内部統制は大きく注目されている要素です。
内部監査とは
内部監査とは、組織内部の人間が行う監査で、内部統制がしっかりと機能しているかをチェックすることです。
具体的には、組織のガバナンス構造とプロセスを評価し、組織の目標と戦略に沿って効果的に機能しているかを確認します。
簡単に表現すれば、「不祥事のリスクがないかどうか」を見るのが内部監査です。
組織が直面するさまざまなリスクを特定しつつ、必要に応じて改善策を提案するのも内部監査の重要な役割です。
組織内のさまざまなレベルで行われ、経営陣に対してフィードバックを提供し、組織の持続的な改善を目指します。
似ている言葉「内部統制監査」って何?
内部統制や内部監査と混同しやすいワードとして「内部統制監査」があります。
内部統制監査とは、企業が作成した内部統制報告書が適正な内容かどうかを、外部の監査法人が監査することです。
内部統制監査は、ミスや不正を防止する目的で行われ、内部統制評価に照らし合わせてチェックされます。
内部統制監査は、社内の人材ではなく外部の監査法人が担当し、会計監査と同じ担当者がその役割を果たします。
一方の内部監査は、内部統制が正常に機能しているかどうかを確認するプロセスであり、内部統制の一部として位置づけられます。
社内の人材によって行われ、法令や社内規定が遵守されているかを確認するのが主な仕事です。
「統制」の文字がないだけではありますが、両者はまったくの別物です。
内部統制の基本的な進め方
内部統制には進めるための基本的な流れがあります。
それは、「環境を整える」→「リスクを見つけて備える」→「ルールを決めて実行する」→「きちんとチェックして報告する」という4つのステップです。
この章では、その進め方を順番にわかりやすくご紹介します。
1.統制環境を整える
内部統制の最初のステップは、社内で内部統制がきちんと機能するための土台をつくることです。
この土台のことを「統制環境」と呼びます。
たとえば、経営者が内部統制の重要性をしっかりと示しているかどうかや、会社の中で役割や権限が明確になっているかどうかが大切なポイントになります。
また、誠実な経営姿勢や、社員一人ひとりがルールを守る意識を持つことも欠かせません。
まずはこのような基本的な環境を整えることから始めることが重要です。
2.リスクを洗い出して対応策を考える
統制環境が整ったら、次は会社の中でどんなリスクがあるのかを洗い出すことが必要です。
たとえば、「お金のやりとりでミスが起きるかもしれない」「不正が行われるかもしれない」といったリスクです。
そして、それぞれのリスクについて「どれくらい重大なのか」「起こる可能性はどれくらいか」を評価します。
その上で、「このリスクにはどう対応するべきか」を考えて、具体的な対策を決めていきます。
リスクへの対応は、経営者だけでなく実際に現場で働く従業員もリスクに気づいて対応できるようにすることが大切です。
3.決めたルールを実際に運用する
リスクに対する対応策が決まったら、次はルールを決めて、それを日々の業務で実行する段階に移ります。
このような具体的なルールや仕組みを「統制活動」と呼びます。
たとえば、以下のようなものがあります。
- ・お金の支払いには必ず上司の承認を得る
- ・一人だけで処理せず、複数人でチェックを行う
- ・誰が何をするか役割を明確にする
- ・業務マニュアルを用意して、迷わず仕事ができるようにする
こうしたルールを日々の仕事の中で実践することで、リスクを防ぎ、業務が正しく行われるようになります。
4.内部統制が機能しているかを評価・報告する
最後に必要なのが、内部統制がきちんと機能しているかどうかを評価することです。
特に上場企業の場合は、J-SOX(日本版SOX法)に基づいて内部統制報告書を作成し、金融庁に提出する義務があります。
内部統制報告書では、会社の内部統制がうまく機能しているかどうかについて経営者がまとめて報告します。
この報告書は、監査人(会計監査人)による確認・監査を受けてから提出します。
もし監査人から「不備がある」と判断された場合は、評価をやり直し、再提出する必要があります。
そのため、日ごろから内部統制が正しく運用されているかを確認することがとても重要です。
内部統制が注目されている背景
内部統制が注目される背景には、相次ぐ日本企業の不祥事が挙げられます。
不祥事と聞くと莫大な損害が発生した事件を思い浮かべる方がいるかもしれませんが、ごく普通の社員が起こした不正報告なども不祥事です。
また、SNSを通じた内部告発により、今まで不正が見過ごされていたことがわかり、多くの企業が内部統制の強化を重視するようになっています。
内部統制には、大きく予防的な統制と発見的な統制の2種類があります。
予防的な統制はリスクがそもそも起きないように手段を講じること、発見的な統制はリスクを伴う事象が発生したことに早期に気づくための仕組みを作ることです。
この2種類がうまく機能すると、不正が発生しやすい機会・リスクを減らして不祥事の芽を摘みながら、業務全体が可視化されて健全な事業活動へと導くことができます。
内部統制に必要なスキルとは?
内部統制は、会社に関わるすべての社員が守るべきルールや仕組みです。
とはいえ、実際のところ内部統制の中でも特に重視されているのが、財務報告に関する内部統制です。
そのため、経理や財務の担当者が中心となって関わる場面が多くなります。
財務報告の内部統制に関わる人材が必要な理由
財務報告に関する内部統制では、正確な財務データをまとめ、外部に報告するまでの一連の流れをチェックする仕組みが必要です。
しかし、実際にはこうした内部統制の業務をしっかりと理解し、担当できる人材が不足している企業も少なくありません。
上場企業のような大きな会社でも、財務報告のための書類やデータをすべて正しくチェックするには、専門的な知識と経験を持った人材が必要です。
そのため、財務報告に関する内部統制の業務を担える人材は、どの企業でも貴重な存在といえるでしょう。
内部統制に対応するために必要な知識と経験
財務報告に関する内部統制の業務を担当するには、まず経理・財務・会計の基礎知識が欠かせません。 さらに、「会社法やSOX法などの法令に関する知識」や「IFRS(国際会計基準)の理解」など、幅広い知識も求められます。
また、知識だけでなく、実際に財務報告や内部統制の実務に関わった経験もあれば、より高く評価されます。
知識と実務経験の両方を備えた人材は、企業にとって非常に頼もしい存在です。
内部統制部門に転職するには
内部統制部門に転職することは、未経験者には難しいです。
財務アドバイザリーやコンサルティングファームなどでの内部統制アドバイザリー業務を経験しているなら、転職できる可能性があります。
また、可能であれば公認会計士資格や、国際的な資格であるCCSA(内部統制評価指導士)、CFE(不正検査士)などの資格をもっていると有利です。
なお、内部統制はすべての社員が関わっており広範なので、内部統制のすべてがわかるプロフェッショナルを目指すことは厳しいでしょう。
しかしながら、財務報告に係る内部統制のプロフェッショナルや、内部監査のプロフェッショナルなど、特定の領域でプロフェッショナルとして活躍する人はいます。
自分がどのプロフェッショナルを目指すのかを明確化しておくと、転職活動をスムーズに行いやすいです。
内部統制内部監査に関わる求人事例
東証プライム上場の製薬企業!内部統制の求人!
| 仕事内容 |
|
・内部統制推進業務 ・J-SOX評価に関する推進業務(内部監査部との連携) ・内部統制委員会の運営 |
| 必要なスキル・経験 |
|
・製造業での内部監査部門業務経験もしくは内部統制部門業務経験 ・J-SOX評価に関する推進、リスクマネジメント推進のご経験が豊富な方 ・渉外力、プレゼンテーション能力 など |
| 想定年収 |
| 700万円 ~ 1100万円 |
IT業界のIPO準備企業!内部統制・内部監査の求人!
| 仕事内容 |
|
<内部統制に関する業務> ・内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案 ・内部統制文書化 <内部監査に関する業務> ・内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施 ・監査対象部門への改善指示及びフォローアップ |
| 必要なスキル・経験 |
| ・上場会社または監査法人における監査業務経験 |
| 想定年収 |
| 700万円 ~ 1000万円 |
プライム上場のグローバルメーカー!内部統制の求人!
| 仕事内容 |
|
・当社及び海外現地法人を含む関係会社の内部統制推進・支援業務(J-SOX) ・内部統制に関わる基本業務 ・本社・子会社の内部統制資料のチェック、文章整理 |
| 必要なスキル・経験 |
|
・経理経験者 ・業務上での英語使用経験 |
| 想定年収 |
| 550万円 ~ 800万円 |
まとめ
内部統制や内部監査、内部統制監査は混同しやすい部分もありますが、定義をきちんと整理すればそれほど難しいわけではありません。
転職の求人での内部統制は、財務報告に係る内部統制など、特定の領域を指しているケースが多く見られます。
転職を視野に入れているなら、ゼネラリストというよりも、特定の領域でのプロフェッショナルを目指すのがおすすめです。
上記のような分野での転職を検討している場合、実務経験や評価される資格をもっていると有利です。
自分の目指したい領域を明確化して、必要な業務経験や資格を洗い出し、地道に活動していくのがよいでしょう。
転職の進め方に疑問を抱いている場合は、転職エージェントを活用するのがおすすめです。
MS-Japanでは、内部統制や内部監査に関わる求人を多数ご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


この記事を監修したキャリアアドバイザー

大学卒業後、カーディーラ・小売業を経験し、2008年からMS-Japanでリクルーティングアドバイザーとキャリアアドバイザーを兼務しております。
会計事務所・監査法人 ・ コンサルティング ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ USCPA ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事
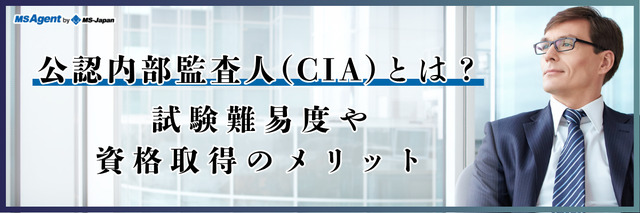
公認内部監査人(CIA)とは?試験難易度や資格取得のメリット

【40代内部監査の転職】求められるスキルや転職事例など

内部監査に向いている人とは?仕事内容や役割、資格について解説

内部監査の志望動機・自己PRはどう書く?経験者・未経験者別にポイントを解説!
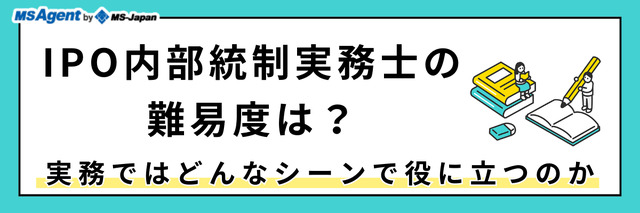
IPO内部統制実務士の難易度は?実務ではどんなシーンで役に立つのか

【30代から内部監査に転職】求められるスキルや経験、CIAについて解説
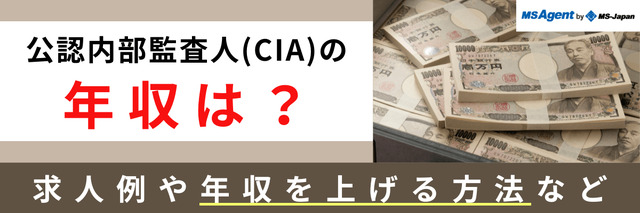
公認内部監査人(CIA)の年収は?求人例や年収を上げる方法など
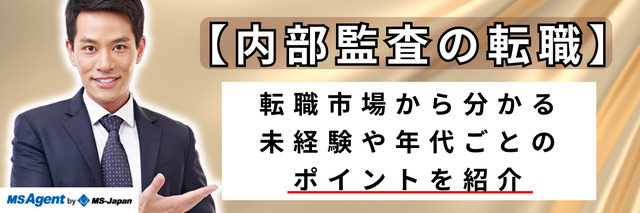
【内部監査の転職】転職市場から分かる未経験や年代ごとのポイントを紹介
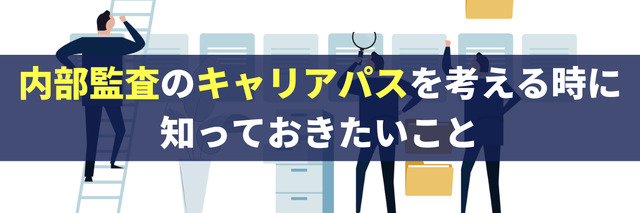
内部監査のキャリアパスを考える時に知っておきたいこと