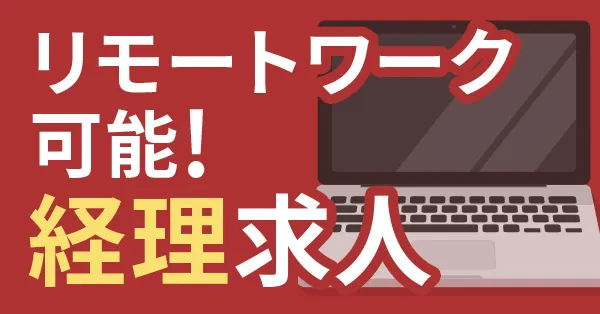ビジネス会計検定は役に立たないって本当?難易度や簿記との違いなどを解説

これから会計業界や経理職としてキャリアを築くため、資格取得を検討している人も多いでしょう。
会計業界は人手不足が深刻化しており、資格取得は就職や転職で大きなアドバンテージになります。
そのため、ビジネス会計検定や簿記といった資格は、キャリアアップを目指す人々から高い人気を集めています。
しかし、「ビジネス会計検定は役に立たない」という意見も見受けられるため、取得すべきか悩んでいる人も少なくありません。
この記事では、ビジネス会計検定の有用性や難易度、簿記との違いなどを解説します。
記事の要約
●ビジネス会計検定は財務諸表を「読み解く」力を養う資格で、業種・職種を問わず活かせる汎用的なスキルにつながる。
●級が上がるほど難易度は上がるものの、簿記検定より合格率は高い傾向にあり、簿記や経理実務の理解を深めるステップとしても有効。
●経理・会計分野のキャリアアップを叶えるなら、今すぐ【転職相談はこちら】へ。
そもそもビジネス会計検定とは?
ビジネス会計検定とは、大阪商工会議所が主催している検定の一つで、財務諸表に関する知識や分析手法について問う試験です。
財務諸表とは、いわゆる決算書のうち、金融商品取引法により上場企業に作成が義務付けられている書類を指します。
特に重要な書類は、企業の経営状況を明らかにする貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書で、これらは「財務三表」とも呼ばれています。
財務諸表を適切に読み取れるようになると、企業の経営状況が健全なのか、それとも注意が必要な状況なのか、安定性・成長性などを判断できるようになります。
ビジネス会計検定で設定されているレベルは、3級・2級・1級の3種類で、それぞれの級の到達目標は以下の通りです。
3級:会計用語や財務諸表の構造・読み方・基本的な分析を理解している
2級:企業の経営戦略・事業戦略を踏まえ、財務諸表の応用的な分析ができる
1級:企業の成長性や課題を判断できる高度な会計知識を有し、財務諸表を含む会計情報の総合的な分析ができる
参考:試験のご紹介|ビジネス会計検定試験
なお、1級受験者のうち、不合格者の得点上位者(120点以上得点した受験者)については、準1級として認定されます。
ビジネス会計検定は役に立たないって本当?
「ビジネス会計検定は役に立たない」と耳にすることがあります。
たしかに、簿記検定などに比べると知名度が高くないため、本当に評価されるのか不安に思う方も少なくありません。
しかし、結論から言えばビジネス会計検定は十分に役に立つ資格です。
資格そのものの知名度よりも、学習を通じて得られる「会計リテラシー」が幅広い場面で活かせるためです。
具体的には、以下のようなシーンで役立ちます。
- 営業や企画担当者:取引先や社内の経営層との会話で財務諸表をもとにした根拠ある提案ができる。
- 財務・経理担当者:日々の仕訳や決算業務だけでなく、経営分析や投資判断のサポートに生かせる。
- 経営者・管理職:数字を読み解く力を身につけることで、自社の財務状況を把握し、戦略的な意思決定に役立てられる。
- 学生・就活生:会計の基礎知識を持つことは、業界を問わず「数字に強い人材」としてアピールできる。
このように、ビジネス会計検定で学ぶ財務諸表の読み方や経営分析の知識は、特定の職種に限らず、ビジネスパーソン全般に役立つ「汎用的なスキル」です。
ビジネス会計検定を取得するメリット
ここでは、ビジネス会計検定を取得するメリットを4つご紹介します。
財務諸表が読めるようになる
ビジネス会計検定で特に力を入れているのが、財務諸表の作成ではなく「分析」です。
財務諸表を読み解けるようになると、企業の状態が良くなっているのか、それとも悪くなっているのかが分かるようになります。
複数の分析指標を駆使して、企業の体力をチェックするスキルは、取引先選びや自身の転職活動にも役立ちます。
株式投資の基礎が身につく
株式ニュースなどは、前提となる知識がないとなぜそのニュースが注目を集めているのか背景を読み取りにくいものです。
しかし、ビジネス会計検定の学習を通じて各種指標に関する知識が習得できるため、株式投資に役立つ基礎知識も自然と身につきます。
会計業界を目指していない場合でも、株式投資に挑戦したい人であれば、ビジネス会計検定を受験するメリットは十分あります。
経営に関わるキャリアを積める
財務諸表を読み解く力は、経営者だけでなく、経営幹部や管理職にも必要です。
自分が所属する部門が、経営にどの程度貢献しているのかを読み解くことで、成果をアピールする材料としても活用できます。
ビジネス会計検定の勉強をしておくと、将来のキャリアアップの布石となります。
簿記の勉強につながる
簿記の資格では、主に仕訳など「財務諸表を作成する」プロセスについて学ぶ必要があります。
これに対してビジネス会計検定では、財務諸表が示す数値の意味を読み解くことに重きを置いているため、間接的に簿記のルールにも自然と触れられます。
よって、ビジネス会計検定を取得後は、簿記検定の受験も視野に入れた学習スケジュールを立てやすくなるはずです。
ビジネス会計検定の試験内容や開催時期、受験料
ビジネス会計検定の試験内容・開催時期・受験料などの受験要項をまとめました。
受験資格
ビジネス会計検定は、学歴・年齢・性別・国籍の制限なく受験することができます。
また、必ずしも3級から受験を始める必要はなく、希望する級から受験して問題ありません。
例えば、3級と2級のように連続する2つの級であれば同時受験が認められています。
仮に2級の合格に自信がない場合でも、3級と同時に申し込むことで、万が一2級が不合格でも3級の合格を確保するといった戦略も可能です。
ビジネス会計検定3級の受験要項
2025年度のビジネス会計検定3級の受験要項は以下の通りです。
| 試験日 | 第37回:2025年10月19日(日) 第38回:2026年3月8日(日) |
|---|---|
| 試験会場 | 札幌、仙台、さいたま、東京、横浜、新潟、金沢、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、山口、松山、福岡の中から受験地を選択 |
| 受験料 | 4,950円(消費税450円) |
| 試験方式 | マークシート方式 |
| 試験内容 | 1.財務諸表の構造や読み方に関する基礎知識
2.財務諸表の基本的な分析について |
| 試験時間 | 2時間 |
参考:受験要項|ビジネス会計検定試験
ビジネス会計検定2級の受験要項
2025年度における、ビジネス会計検定2級の受験要項は以下の通りです。
| 試験日 | 第37回:2025年10月19日(日) 第38回:2026年3月8日(日) |
|---|---|
| 試験会場 | 札幌、仙台、さいたま、東京、横浜、新潟、金沢、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、山口、松山、福岡の中から受験地を選択 |
| 受験料 | 7,480円(消費税680円) |
| 試験方式 | マークシート方式 |
| 試験内容 | 1.財務諸表の構造や読み方、財務諸表を取り巻く諸法令に関する知識
2.財務諸表の応用的な分析について |
| 試験時間 | 2時間 |
参考:受験要項|ビジネス会計検定試験
ビジネス会計検定1級の受験要項
2025年度における、ビジネス会計検定1級の受験要項は以下の通りです。
| 試験日 | 第38回:2026年3月8日(日) ※1級のみ第38回の実施はありません。 |
|---|---|
| 試験会場 | 札幌、仙台、さいたま、東京、横浜、新潟、金沢、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、山口、松山、福岡の中から受験地を選択 |
| 受験料 | 11,550円(消費税1,050円) |
| 試験方式 | マークシート方式および論述式 |
| 試験内容 | 1.会計情報に関する総合的な知識
2.財務諸表を含む会計情報のより高度な分析について |
| 試験時間 | 2時間30分 |
参考:受験要項|ビジネス会計検定試験
ビジネス会計検定の難易度や合格率は?
ビジネス会計検定の難易度は、3級<2級<1級の順に上がり、級が上がるごとに合格率も低くなる傾向にあります。
以下、ビジネス会計検定試験の公式サイトで公開されている各種データを引用しながら、各級の難易度について解説します。
ビジネス会計検定試験の合格率
ビジネス会計検定試験における、各級の2021年3月~2025年3月までの合格率は、以下の通りです。
| 回 | 実施年月 | 1級 | 2級 | 3級 |
|---|---|---|---|---|
| 第36回 | 2025年3月 | 22.9% | 34.5% | 50.6% |
| 第35回 | 2024年10月 | 実施なし | 43.7% | 56.5% |
| 第34回 | 2024年3月 | 26.4% | 44.6% | 70.9% |
| 第33回 | 2023年10月 | 実施なし | 46.7% | 70.2% |
| 第32回 | 2023年3月 | 21.3% | 59.1% | 61.7% |
| 第31回 | 2022年10月 | 実施なし | 53.3% | 67.2% |
| 第30回 | 2022年3月 | 10.8% | 54.2% | 63.5% |
| 第29回 | 2021年10月 | 実施なし | 52.1% | 68.9% |
| 第28回 | 2021年3月 | 24.4% | 51.5% | 67.7% |
参考:試験結果・受験者データ|ビジネス会計検定試験
実施回によって変動はありますが、3級は合格率が50%を超えることが多く、比較的挑戦しやすい級といえるでしょう。
2級も半数近くが合格する回が多く、しっかり対策すれば十分に合格が可能です。
しかし、1級になると難易度が大きく上がり、合格率は約20%になります。
各級の難易度と合格ライン
ビジネス会計検定試験の、各級の難易度と合格ラインは以下の通りです。
| 級 | 難易度 | 合格ライン |
|---|---|---|
| 3級 | 基本的な事項を確認するレベルの試験 難問や奇問といった問題はほとんどない |
100点満点中 70点で合格 |
| 2級 | 基礎知識をビジネスに応用することを想定したレベル 会計経験者向けの問題も多く、3級よりやや難しい |
100点満点中 70点で合格 |
| 1級 | 論述式が加わり、マークシートの選択肢に頼らず、自力で解答しなければならない 難しい計算や専門知識が問われる問題も多く、足切りもあるので、総じて難易度は高い |
論述式50点以上 +全体で140点以上の得点 (200点満点) 不合格者のうち、120点以上の受験者については「準1級」として認定 |
参考:級別内容・出題範囲|ビジネス会計検定試験
3級・2級と比較して、1級はより専門的な知識が求められ、計算・論述にも時間を割く必要があります。
論述問題に関しては、解答用紙のスペースが限られていることもあり、伝えるべきことを簡潔にまとめる技術も求められるでしょう。
ビジネス会計検定の勉強時間
ビジネス会計検定試験の受験にあたり、どのくらいの勉強量が必要なのか把握する上で参考となるのが、勉強時間の目安です。
以下、3級~1級合格に必要な勉強時間の目安と、勉強方法について解説します。
3級合格に必要な勉強時間の目安
ビジネス会計検定3級は基本的な問題が中心であり、公式テキスト・過去問題集を使って勉強すれば十分に合格を狙えるレベルです。
合格に必要な勉強時間としては、50~100時間を想定しておけばよいでしょう。
なお、必須ではありませんが、簿記・会計の知識があると、その分、理解も早まります。
2級合格に必要な勉強時間の目安
ビジネス会計検定2級は、3級の内容に加えて連結会計・損益分岐点分析などが出題範囲に含まれ、3級と比較して多少難しくなります。
しかし、簿記・会計の知識がある人にとっては、比較的取り組みやすい問題も多くあります。
公式テキスト・過去問題集を使って取り組んだケースを想定すると、合格に必要な勉強時間は、100〜200時間が目安となるでしょう。
1級合格に必要な勉強時間の目安
ビジネス会計検定1級は、ある意味では経営層に匹敵するレベルが求められ、経理財務管理職・役員レベルの実力を問われます。
出題範囲が広く、知識を体系的に理解している必要があるため、公式テキスト・過去問題集を使った勉強だけでは論述試験に不安を感じる方も多いです。
合格に必要な勉強時間は、300~500時間が目安となります。
いきなり2級や1級からの受験ってアリ?
ビジネス会計検定は、年に1~2回しか試験が開催されないため、3級からではなく2級・1級からの受験を検討する人も多く見られます。
しかし、初めてビジネス会計検定を受験するのであれば、まずは3級からの受験をおすすめします。
ビジネス会計検定は、数学のように基礎を積み上げて応用力を養っていく学習が効果的な試験です。
そのため、3級で基礎を固め、2級で応用力を養い、最後に1級でより発展的な内容に挑戦するという流れが、最もスムーズな学習ステップです。
2級の問題は3級の知識が前提となっているため、知識の抜け漏れを防ぐためにも、まずは3級から受験するのが望ましいでしょう。
仮に、3級を飛び越えて2級を取得できたとしても、実際の業務で活用できない場合もあります。
ビジネス会計検定と簿記検定の違い
会計に関する資格の中で、日本でもっとも知名度が高いものの一つが「簿記検定」です。
日商簿記や全経簿記は、1級の合格が税理士試験の受験資格に数えられるなど、社会的な信用度が高い資格といえます。
しかし、簿記検定とビジネス会計検定は、そもそも試験の成り立ちや目的が異なります。
以下、それぞれの違いについて解説します。
試験内容の違い
ビジネス会計検定と簿記検定の違いを端的にまとめると、財務諸表を「読み解く」のか「作成する」のかという違いがあります。
仕訳や試算表作成など、主に経理の実務で財務諸表を「作成する」ことが多いのであれば、簿記を選択するのが妥当な判断です。
これに対して、会計情報を「読み解く」スキルを学ぶビジネス会計検定は、幅広い分野で役立てられます。
経営状況を踏まえた提案が必要な営業・販売職、購入すべき株式を決めるために財務諸表の分析が必要な投資家、取引先を見極めたい経営者など、それぞれのニーズに対応した試験内容となっています。
合格率の違い
ビジネス会計検定は、日商簿記検定に比べて、合格率が高い傾向にあります。
以下、大まかな合格率の違いをまとめました。
| 級 | ビジネス会計検定 (第32回~第36回の平均) |
日商簿記 (第166回~第170回の平均) |
|---|---|---|
| 3級 | 62.0% | 35.3% |
| 2級 | 45.7% | 23.7% |
| 1級 | 23.5% | 13.2% |
参考:
試験結果・受験者データ|ビジネス会計検定試験
簿記 受験者データ|商工会議所の検定試験
ビジネス会計検定の合格率は、日商簿記検定と比較して2・3級は20~30%ほど、1級は10%ほど高いことがわかります。
よって、合格率が少しでも高い会計の試験を受験したいのであれば、ビジネス会計検定がおすすめです。
なお、簿記検定について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
あわせて読みたい
希少性の違い
ビジネス会計検定は、2007年7月からスタートした、比較的新しい資格です。
受験者数は年々増えているものの、1954年11月から行われている簿記検定と比較すると、相対的に合格者は少ない検定試験です。
合格者が少ないということは、財務諸表等を読み解くスキルを持っている人材、あるいはそれをアピールできる人材が、日本ではまだまだ少ないとも解釈できます。
よって、ビジネス会計検定に合格することで、自らの希少性を高めることにつながります。
まとめ
ビジネス会計検定は、業種・職種を問わず幅広い分野で活用できる資格です。
財務諸表を作成するのではなく、情報を読み解いて活用する方法を学ぶ試験のため、ビジネスパーソンにとっては重要度の高い資格といえるでしょう。
級が上がるにつれて、難易度も高くなるため、合格するにはしっかり対策を講じる必要があります。
同じ会計分野の簿記検定と比較すると合格率は総じて高い傾向にありますが、受験者数はまだ少ないため、合格することで財務諸表を分析できる希少な人材としてアピールできます。
ビジネス会計検定以外にも、経理のキャリアに役立つ資格は多くあります。
転職やキャリアアップなど目的別におすすめの資格を知りたい方はこちらもご確認ください。
- #ビジネス会計検定
- #ビジネス会計検定 合格率


この記事を監修したキャリアアドバイザー

カナダ州立大学卒業後、新卒でMS-Japanへ入社。求人企業側の営業職を経験した後、2014年にキャリアアドバイザーへ異動。
2016年からは横浜支社にて神奈川県内の士業、管理部門全職種を担当し、現在は関東全域の士業、管理部門全職種を担当。
経理・財務 ・ 人事・総務 ・ 法務 ・ 経営企画・内部監査 ・ 外資・グローバル企業 ・ 会計事務所・監査法人 ・ 役員・その他 ・ IPO ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ USCPA ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事

DX時代に求められる30代の経理スキル|会計システム・RPA活用力(後編)

内部統制・監査対応に強い30代経理はなぜ採用ニーズが高いのか?(後編)

【経理キャリアマップ】上場企業の経営企画責任者になるには?

第二新卒のUSCPA取得者は転職に有利!ポイントと事例を解説

証券アナリスト資格の難易度・勉強時間は?転職で役に立つの?
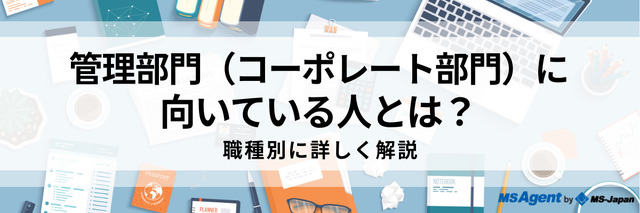
管理部門(コーポレート部門)に向いている人とは?職種別に詳しく解説

実務未経験でもUSCPAで転職できる?年代別ポイントや求人例など

未経験でも転職はできる?MS-Japanの転職支援サービスを紹介!
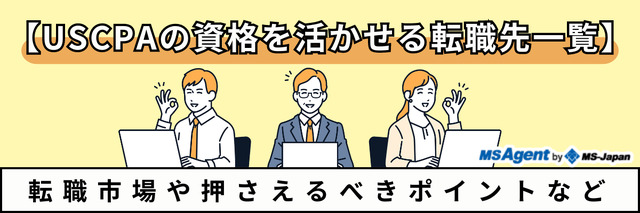
【USCPAの資格を活かせる転職先一覧】転職市場や押さえるべきポイントなど