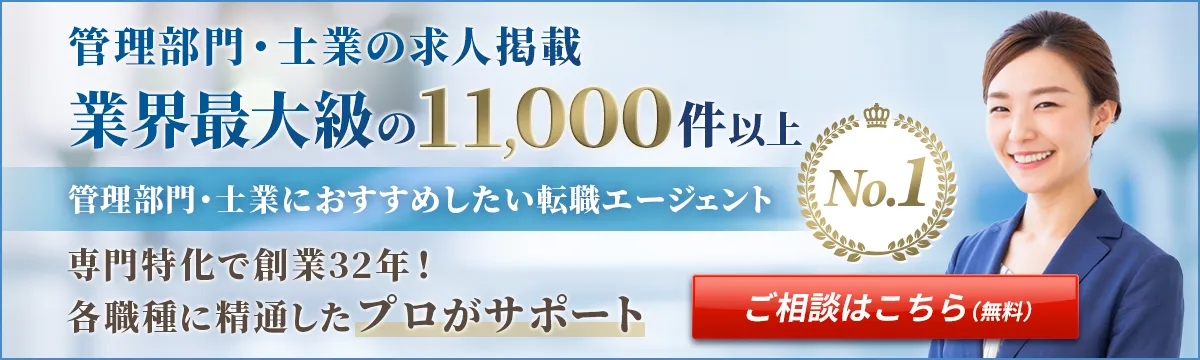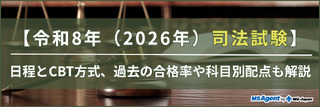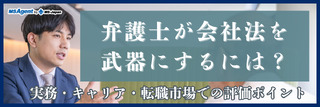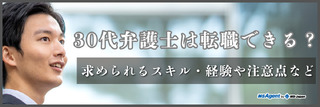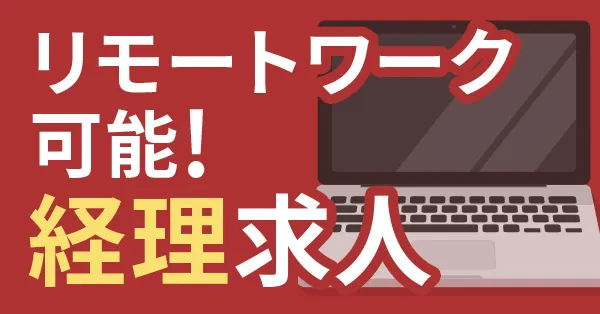企業内弁護士に転職したい方へ!個人受任の取り扱いには要注意!

法律事務所から企業内弁護士へ転職する場合、事件を個人受任できるかどうかが気になることも多いでしょう。
企業は、企業内弁護士の個人受任を認めるのでしょうか?
また、今後も個人受任を継続したい場合には、どうすべきなのでしょう?
企業内弁護士への転職は、個人受任している案件を転職先の企業に確認
法律事務所から企業内弁護士に転職する際には、個人受任している案件を転職先に確認しましょう。
企業内弁護士の個人受任を認めるかどうかは、転職先企業によって対応が異なります。
個人受任している案件を転職先の企業に確認すれば、間違いはありません。
企業内弁護士の個人受任を禁止している企業も
企業内弁護士の個人案件を認めるかどうかは、企業によって対応が異なり、個人受任を禁止している企業もあります。
企業内弁護士の個人受任に対する企業の一般的な対応、パートタイムの場合、および国選弁護人などの公益活動の場合はどうなのかについて見てみましょう。
・企業内弁護士の個人受任に対する一般的な対応
企業内弁護士の個人受任に対する一般的な対応は、企業の雇用契約や就業規則などの内容によって決められます。
副業を一切禁止している企業は、企業内弁護士の個人受任も禁止されています。
ただし、上司の許可がおりれば副業を認める企業もあります。そのため、副業を禁止している企業においては個人受任する案件について上司に逐一確認する必要があります。
一般に、企業内弁護士の個人受任を認める企業はあまり多くありません。
・パートタイムの場合はどうなのか
企業内弁護士として週3回などのパートタイムで勤務する場合は、一般的に勤務時間以外であれば自由な個人受任が認められます。
・国選弁護人などの公益活動の場合はどうなのか
弁護士会によっては、国選弁護人や当番弁護士などの公益活動が義務付けられていることもあります。
企業内弁護士に対して、公益活動についても認めない企業もあります。
一方で、公益活動なら、業務に支障がない範囲で認める企業や、積極的に推奨する企業もあります。
今後も個人受任を継続したい場合は、どうすべきか
以上で見たように、企業内弁護士の個人受任についての対応は、企業によって異なります。
今後も個人受任を継続したい場合には、転職先として個人受任を認める企業を選ぶ必要があるでしょう。
ただし、企業内弁護士が個人受任をする際には、いくつか注意しなければならないことがあります。それらを以下で見ていきましょう。
<企業が事件に関与しないよう注意>
企業内弁護士であっても、弁護士が個人受任した事件について企業が関与することは一切できません。
事件の処理内容に関与するのは当然のこととして、案件のあっせんなどに関与した場合でも、弁護士法72条や74条において禁止されている非弁行為に当たる可能性がありますので注意しましょう。
<情報管理を徹底する>
弁護士は、受任する事件について守秘義務を負うため、情報管理を徹底しなければなりません。
特に注意しなければならないのは、社内の電話やファックスを使用する場合です。
社内の他の従業員に電話やファックスの内容が漏れないよう、細心の注意を払いましょう。
また、企業のメールアドレスは、情報が漏れてしまう恐れがあります。
個人受任した事件についてのやり取りに際しては、個人のメールアドレスを使用することが望ましいといえるでしょう。
<社内の従業員からの相談は利益相反になることも>
企業内弁護士として勤務した場合には、社内の他の従業員から法律的な相談を個人的に持ちかけられることが考えられます。
その場合には、利益相反が生じたり、あるいは弁護士としての守秘義務と所属企業に対する報告義務とが衝突したりすることがあり得ますので慎重に対処しましょう。
報酬を得ない相談であったとしても、弁護士への相談は弁護士の業務となります。
利益相反が起こりやすい相談の例として、セクハラやパワハラなどがあります。
セクハラやパワハラでは、所属企業とセクハラ・パワハラを受けた従業員の利害が対立するからです。
また、企業内不倫や借金などの相談は、その内容が相談者に対する企業の評価を左右するものとなります。
したがって、弁護士としての守秘義務と企業への報告義務が衝突する可能性が高まります。
利益相反や守秘義務と報告義務の衝突を防ぐためには、従業員からの相談を受けるに当たり、自分が企業の従業員の立場であることをしっかりと説明することが重要です。
また、相談の途中で利益相反になることがわかった場合は、相談を中止したうえで他の弁護士を紹介するなどの対処も必要となるでしょう。
<企業の評判を損なわないように配慮>
個人受任した事件の内容によっては、担当弁護士の所属企業と事件がマスコミの報道などで結び付けられてしまうことがあります。
そのようなことにより、所属企業の評判を損なうことがないように十分に配慮しましょう。
まとめ
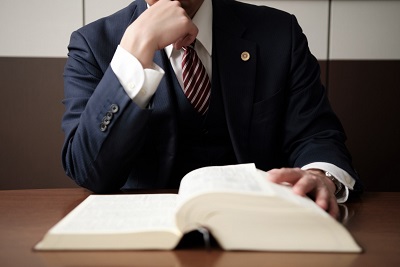
企業内弁護士の個人受任に対する対応は、企業によって異るため、転職先の企業が個人受任を認めるかどうかをあらかじめ確認することが必要でしょう。
また、個人受任を認める企業に転職した場合でも、個人事件に従事するに際しては、弁護士の守秘義務に違反したり、企業の評判を落としたりなどのことがないよう、慎重に対処していきましょう。
<参考>
・ 日本組織内弁護士協会「よくある質問」
・ 第一東京弁護士会「企業内弁護士 雇用の手引き」
・ 日本弁護士連合会「企業内弁護士の採用に関するQ&A」


 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事

三大国家資格とは?試験内容と難易度、五大国家資格についても解説

行政書士は企業法務に転職できない?資格の活かし方や求人例など
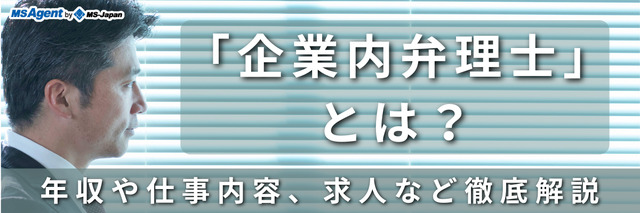
「企業内弁理士」とは?年収や仕事内容、求人など徹底解説

未経験でも転職はできる?MS-Japanの転職支援サービスを紹介!

検事のキャリア・仕事内容・給与やその後のキャリアパスについて
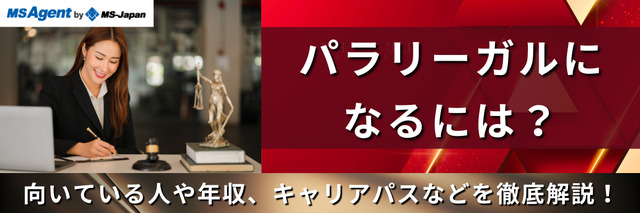
パラリーガルになるには?向いている人や年収、キャリアパスなどを徹底解説!

プライバシー侵害の判断基準とは?

後を絶たない業務上横領罪...... 中小企業で深刻化?

「みなし公務員」とは?一歩間違えれば贈収賄の可能性も!?