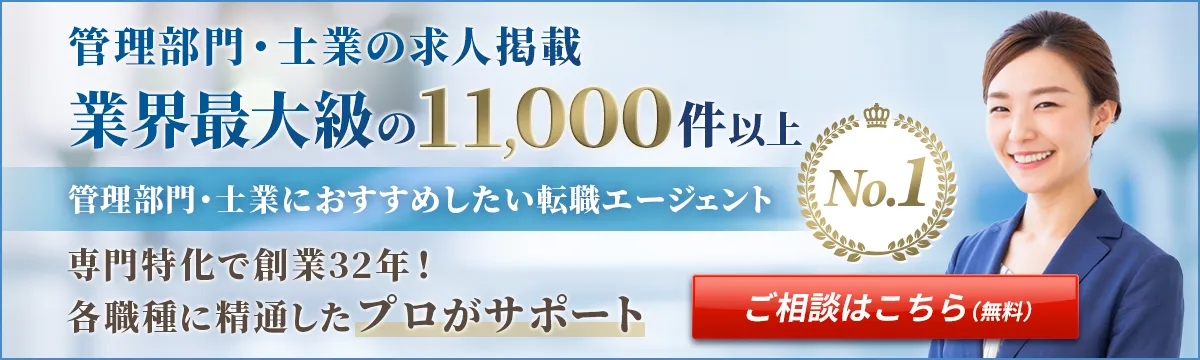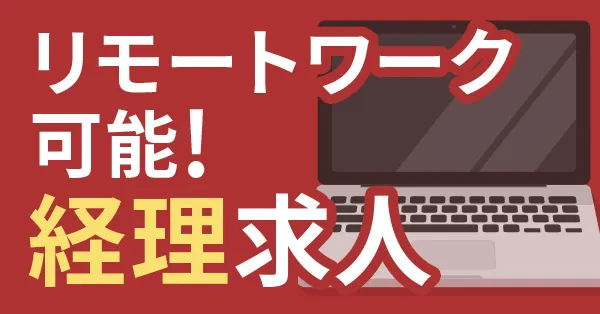企業法務に必要な基礎知識とは
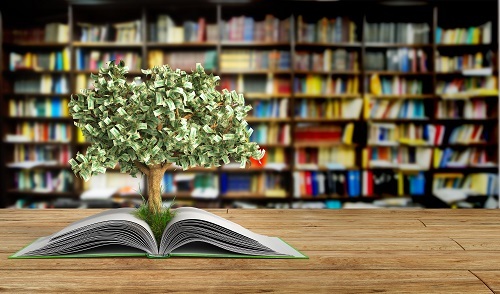
法律について知識のある方であっても、企業法務としてどのような仕事に従事するのかについてはよく分からないという方は少なくありません。
一般的には弁護士・行政書士などの法的な専門職に就いている方であれば、その業務をカバーできるものと考えがちですが、根本的に士業とは立ち位置が異なるため、やるべき仕事も違ってきます。
初心者はもちろん、仮に法曹経験者であったとしても、その点をわきまえて仕事に臨まなければ、認識の違いから思わぬ失敗をする可能性も十分あります。
今回は、そんな企業法務に必要な基礎知識についてご紹介します。
企業法務が行っている日常業務にはどのようなものがあるのかを確認しよう
企業法務が携わる業務で日常的に行われている業務というものは、他の事務職に比べるとそう多くありません。
中にはシステマチックな業務もありますが、基本的に法務職はケースごとの解決策を求められる場面が多いことから、経理職などのように決められた枠をなぞるような仕事にはなりません。
しかし、多くの方は企業法務と聞くと「会社における法の番人」をイメージし、どちらかというと型にはまった仕事をしなければならないものと考えがちです。
結論から言えば、企業法務が取り扱う業務というものは、主にイレギュラーケースということも珍しくないのです。
日常業務を挙げてみると、以下のような仕事が挙げられます。
- 契約や取引に関する業務
- 社内の機関を会社法に基づいて運営する業務
- 法律に詳しくない社員のサポート業務
- 紛争、訴訟にかかる対応業務
- 国内、海外の法制度調査業務
- コンプライアンス、社内規定に関する業務
これらの業務のうち、ルーティーンの要素がからむ部分はそう多くありません。
機関運営などは例年同様に進める部分もあるでしょうが、法改正などの情報が適切に反映されていなければならないため、毎年同じ流れになるとは限りません。
思いのほか、臨機応変な対応が求められる職種なのです。
企業法務をこなしていくうえで最低限必要なスキルは、法律の解釈に柔軟性を持たせること
企業法務のスキルとして、当然社内で必要な法律に関する知識は必須要件です。
しかし、ここでいう「知識」というのは、必ずしも詳細な記憶力を必要とするものばかりではありません。
むしろ、法律を理解したうえで、それを会社でどれだけ活かせるのかを求められるのが企業法務の仕事です。
法務の世界では、ときに「合法的なルール違反」という言葉に近いやり取りが行われることがあります。
これは、法律をどれだけ会社にとって有利に働かせるのかを考える際の例えでもあります。
弁護士などを例にとれば、このあたりが企業法務と士業との大きな違いになります。
弁護士はその豊富な法律知識によって、現行法では「こういうことはダメ」とされている条件を特定し、企業にはそのルールを逸脱しないように指導しますし、そのうえで万一裁判に臨んでも勝てるように考えます。
しかし、企業法務の場合は考え方のベクトルがある意味逆に働いており、社内で法律を適用する場合「どこまでがOKなのか」を探るスタイルになります。
よって、弁護士が社内弁護士として活動する場合、そのあたりが企業の意識との間にギャップが生まれる一因となります。
法律によって企業に足枷を与えるのではなく、翼を与えることが、企業法務には求められているのです。
企業法務として活躍できるスキルを考えるなら、知識よりも人間力が大事
企業法務という職種において誤解されがちなのは、目に見えるスキル面だけではなく、見えないスキルも大切だということです。
もちろん、活躍するためには契約書作成などの実務面で高い専門スキルが求められますし、文献や判例を迅速にリサーチできる能力も問われます。
しかし、意外と経験者でも穴になりがちなのが、いわゆる「コミュニケーション能力」です。
他部署や幹部とのやり取りも比較的多いため、プレゼン能力や根回しなどの交渉術なども、場合によっては必要になります。
それも全ては、企業が正しい方向に進むための努力になるのですが、全社員が企業法務のスタッフに対して協力的とは限りません。
企業法務という仕事に発展性を求めるのであれば、以下のような能力が求められると言えます。
- 自社の経営に即した法律知識に精通していること
- 法律知識を最大限柔軟に解釈できること
- 実務レベルで高い技術を有していること
- 社内におけるコミュニケーション力、交渉力を備えていること
初心者の方は実務に慣れるのはもちろん法律を応用することを学び、上級レベルを望むなら、実務の実力とコミュニケーション力を身に付けることを意識しましょう。
まとめ
企業法務として身に付けておきたい基礎知識は、最低限社内での業務に必要な法律知識であることは言うまでもありません。
しかし、その知識を自分で応用し、複雑な社内の環境に適応させていくためには、どこまで幅広く文言を解釈できるかにかかっています。
それができるようになったら、今度はその知識を社内の人材に伝える技術を身に付けなければなりません。
ステップアップを考えるのであれば、知識の取得→応用力の取得→コミュニケーション力・交渉力の取得の順番で取り組んでみるのがよいでしょう。
【この記事を読んだ方におすすめのサービス】
◆管理部門・会計・リーガルの転職ならMS Agent!無料であなたの転職活動をサポート!
◆≪転職で譲れないポイントを相談&発見!≫無料転職相談会・無料転職セミナー


 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事

会社法改正は法務人材のキャリアをどう変える?転職市場で評価される知識と経験(後編)
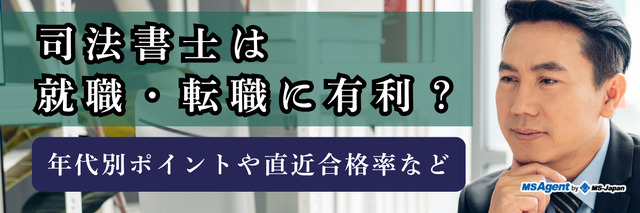
司法書士は就職・転職に有利?年代別ポイントや直近合格率など

行政書士は企業法務に転職できない?資格の活かし方や求人例など
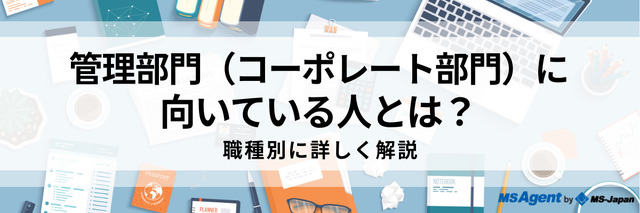
管理部門(コーポレート部門)に向いている人とは?職種別に詳しく解説

未経験でも転職はできる?MS-Japanの転職支援サービスを紹介!
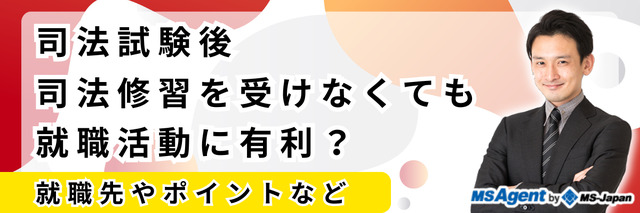
司法試験後、司法修習を受けなくても就職活動に有利?就職先やポイントなど
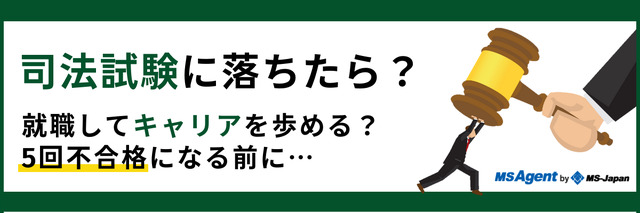
司法試験に落ちたら? 就職してキャリアを歩める? 5回不合格になる前に…

司法試験に年齢制限はある?合格者の平均年齢や最年少・最高齢のデータについても解説!

検事のキャリア・仕事内容・給与やその後のキャリアパスについて