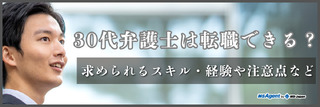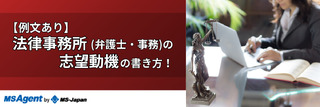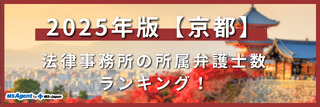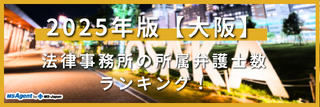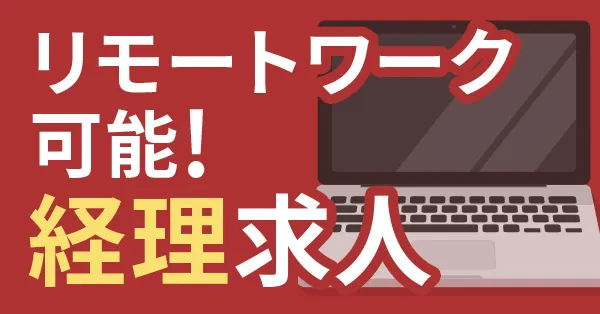弁護士の就活スケジュールは?就活の進め方や就活準備について解説

弁護士を目指している司法試験受験生もしくは合格者にとって、司法試験に次いで重要となる勝負の場が就職活動です。
せっかく司法試験を突破しても、自分の適性に合わない職場や希望に合わない職場に妥協して就職すると、働きがいのない弁護士生活を送ることにもなりかねません。
志望する職場に勤務できるように、事前に十分な就活対策をしておくことが大切です。
そこで今回は、弁護士の就職活動のスケジュールとその進め方、準備の方法について詳しく解説します。
弁護士(司法試験受験者)はいつ就職活動をすればいいのか?
弁護士の就職活動に適した時期は、就職先によって若干異なります。
希望する就職先の採用スケジュールを把握していなければ、就活がうまくいかない可能性もあるため注意が必要です。
主な就職先である法律事務所と一般企業の採用スケジュールの違いについて、詳しく解説します。
法律事務所に就職する場合
法律事務所に就職する場合、就職活動を行う時期は司法試験の合格発表の前後に分かれます。具体的な時期について解説します。
合格発表前
まず、司法試験の合格発表の前が1つ目のタイミングです。司法試験を受験した後の7月下旬からを目安としてください。
この時期から五大法律事務所(四大法律事務所)をはじめとした企業法務系事務所が積極的に採用活動を開始します。 個別訪問や集団での事務所説明会が行われます。
まだ就活を始めていなかったとしても、事務所の説明会やインターン、サマークラーク、セミナー、食事会(会食)、勉強会などに参加をしておくことで、事業や業務に関する情報を集めることができます。
実際に現場で働く弁護士から話を聞くことができる機会でもあるため、上手に活用しましょう。
なお、人気のある事務所のサマークラークは、司法試験後にはすでに受付を締め切っている場合が多いため、企業法務・渉外事務所を希望するのであれば、司法試験前からの活動(申し込みや情報収集)が必須です。
合格発表後
おおよそ11月~1,2月で、就活が本格化してくる時期でもあります。
大手以外の事務所の求人数も増加してきます。司法修習が始まる前に、興味のある事務所との関係性を構築しておきましょう。
合格発表直後には東京三弁護士会の合同就職説明会が日本弁護士連合会および関東弁護士会連合会との共催で実施されます。
一般企業に就職する場合
弁護士の就職先としては、法律事務所のほかに一般企業のインハウスローヤー(企業内弁護士)という選択肢もあります(詳しい仕事内容については後述します)。
インハウスローヤーの就職活動は、司法試験の合格発表の前後(10月中旬~12月中旬)に来期の司法修習生の募集が開始します。
エントリー受付は司法修習が始まる2月または3月あたりで終了するケースが多いため、インハウス就職を目指す場合は司法修習が始まるまでに就職活動を行う必要があるでしょう。
企業によって詳しいスケジュールは異なりますが、大まかな採用までの流れは以下の通りです。
- 企業説明会→エントリー→一次選考(書類)→面接(1,2回)→最終選考→内定連絡
なお、とくにエントリーの期限を設けず、通年で募集をかけている企業もあります。
個々の募集状況については各企業のホームページや、弁護士専門の就職・転職サイトで情報を収集しましょう。
サマークラーク参加もおすすめ!
本格的な就職活動に入る前に、夏休みを有効活用してサマークラークに参加するのもおすすめです。
なぜサマークラークに参加した方がよいのか、以下に詳しく紹介しましょう。
サマークラークとは?
サマークラークとは、法律事務所が夏季休暇期間に実施する研修制度のことです。
ロースクール生や法学部生、予備試験および司法試験合格者などが対象で、過去の判例の調査や書類作成の補助などを行います。
サマークラークに参加することで、実際の弁護士業務を体験できるのは大きなメリットです。
さらに事務所の雰囲気を知ることができ、同年代の仲間や先輩弁護士との人脈が築ける貴重な機会でもあります。
サマークラークから内定につながるケースも!
サマークラークへの参加が内定に有利に働くこともあります。
大手事務所などではサマークラークを採用活動の一部として考えるところも多く、実際に仕事を経験してもらって、優秀で熱意のある、事務所にマッチした人材を見極めています。
実際、サマークラークに参加した人が採用されることは珍しくありません。
また、事務所によっては、サマークラークの参加を採用条件にしているところもあります。
三会合同説明会に参加してみよう!
サマークラークとともに、弁護士の就職活動で活用したいのが「三会合同説明会」です。
以下に概要やメリットを紹介します。
三会合同説明会とは
「三会合同説明会」とは、その年の司法修習予定者を対象に、毎年司法試験の合格発表時期に行われる東京三弁護士会の合同就職説明会のことです。
東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の3弁護士会が主催、日本弁護士連合会・関東弁護士会連合会が共催で、弁護士を採用する予定のある弁護士事務所や企業が合同で就職説明会を行います。
近年はオンラインでの開催となっており、東京だけでなく全国の法律事務所や企業が参加しています。
司法修習予定者にとっては多数の企業や法律事務所の情報を得られる貴重な機会で、2023年度は602名の申し込みがありました。
三会合同説明会に参加するメリット
法律事務所は一般企業の新卒採用と比べ、大々的に募集をかけることは少なく、一般的な就職活動と比べて情報が得にくい状況になっています。
「三会合同説明会」に参加すると一度に多くの企業や法律事務所の採用情報を得ることができます。
一方で、参加する事務所1所当たりの持ち時間は少ないため、深く情報を収集するというよりも、興味のある事務所を探すための機会として活用しましょう。
説明会で興味を持った事務所に直接連絡・申し込みをして、より深く情報収集するといいでしょう。
また、近年はオンライン開催となっているため、遠方からでも参加が可能で、移動にかかる時間や手間を省くことができます。
1日の開催枠は6コマで、開催期間は5日間、計30枠の中から好きな枠を複数選べるため、忙しい人でも参加しやすいスケジュールになっています。
弁護士の年齢は就職活動に影響するのか?
一昔前は転職活動における年齢が大きな障壁であるというイメージが広まっていましたが、近年は人材不足から売り手市場となり、転職条件は大きく改善されています。
しかし、選考では今までの実績や成果が問われることは変わりありません。
では、弁護士の場合はどうなるのでしょうか。
法律事務所や企業内弁護士、さらに任期付公務員など、それぞれの人材募集において、年齢制限は設けられていませんが、大手法律事務所の場合、若い年齢の方が有利に働くケースもあります。これは長期的な視点で、人材育成を図るためです。
若いといっても、司法試験自体が法科大学院を修了した後に受験するため、就職活動を始める年齢は25歳前後です。
一方、若年層の人材を一から育成するよりも、即戦力として起用したい法律事務所は、年齢が高い人材でも積極的に採用しています。
実績を積み、実務能力を保証されている人材はやはり重宝されるものです。
その場合も、一般企業への転職活動と同じように、キャリアと実績が問われます。とくに転職活動においては、以前の職場での働きや、どのような専門分野で経験をしてきたのかが重視されます。
選考過程や面接で今までの経験を問われた際、先方が納得する、もしくは評価に値する実績があればスムーズに採用まで進めることができるでしょう。
就職活動に臨む前に調べること
就職活動は準備が大切です。業界研究や自己分析などやるべきことはありますが、とくに調べておくべきことは仕事内容です。
弁護士の就職先には大きく分けると2つの選択肢があります。
法律事務所で弁護士として働くパターンと、インハウスローヤー(企業内弁護士)として企業に就職するパターンです。
どちらの働き方が自分に適しているのか、希望に近いのかを考えて選択します。 就活を開始する前に、それぞれの仕事の特徴や役割を理解しておきましょう。
では、法律事務所とインハウスローヤーそれぞれの業務を具体的に紹介します。
法律事務所
法律事務所では、社会で起きているあらゆる問題を扱います。
弁護士は、民事事件から刑事事件、さらには企業法務まで、さまざまな案件について法的な解決をしていきます。
- ・民事事件:私人間で法的な紛争(相続や離婚、借金など)が生じた場合、個人や法人が起こす訴訟
- ・刑事事件:被告人が犯罪行為(窃盗や傷害、殺人など)を行ったのか審理し、検察官が処罰を求める訴訟起訴
- ・企業法務:企業活動に関する法律相談や予防法務、戦略立案などの法律事務全般
- ・その他:企業の取引基本契約やライセンス契約、業務委託契約、販売代理店契約、権利関係やコンプライアンス、M&A、倒産などの各種法務
基本的には日本の法律に基づいた案件が中心ですが、国際業務に強い法律事務所もあります。
国際法務に関する業務としては、グローバル関連の日々の法律相談やクロスボーダー取引、英文契約、ジョイントベンチャー、海外子会社管理、さらにはADR(裁判外紛争解決手続)、PL事件など国際紛争や国際仲裁などに関わります。
グローバル化が進展する中で、アウトバウンド案件・インバウンド案件を取り扱う法律事務所も珍しくありません。
インハウスローヤー(企業内弁護士)
一般企業に就職をして、主に法務部所属の法務担当として働きます。
主な業務は、企業内で発生する法務問題を扱うことです。
近年、コンプライアンスの徹底が企業に求められている中で、企業法務はその中核を担う、重要な業務です。
下記の業務を中心に担当します。
- ・契約・取引法務:売買契約や秘密保持契約・業務委託契約に関する書類作成・確認・審査・交渉、手続
- ・株主総会・取締役会の準備・運営
- ・株式や新株予約権・社債の発行・分割に関する法的業務
- ・定款作成・変更
- ・グループ会社・子会社の設立のための法的業務
- ・社内の法律相談
- ・社員のコンプライアンス研修 等
この数年で、IoTやクラウド化、DX推進などビジネス環境は大きく変革しつつあります。
この中で知的財産マネジメントやデジタル法務に関する仕事を遂行することも少なくありません。
また、インハウスローヤーでも海外進出をしている企業であれば、国際的な業務に携わる機会もあります。
法律事務所へ就職した場合は、業務分野がかなり多種多様です。1人あたりの業務量も多く、土日祝など休日が取りにくいこともあるといわれます。
しかし、実力を磨いて、将来的に独立・開業を目指すことも可能です。
一般企業にインハウスローヤーとして就職した場合、企業の就業規則に従って働くことができるため、オンオフの切り替えやワークライフバランスが取りやすいこともメリットです。しかし、仕事内容は特定の分野に限られるため、業務が単調になる傾向にあります。
また、法律事務所への転職や独立開業を目指す場合には、少し不利になるでしょう。
弁護士が就職活動時に必要なもの
弁護士が就職活動を行う際、以下の書類が必要になります。
- ・履歴書および自己PR書
- ・司法試験の成績通知書
- ・大学(学部)での成績表
- ・ロースクールの成績表(ロースクール卒業後に司法試験に合格した場合)
これら書類は履歴書と合わせて志望先に提出するのが一般的です。
履歴書は趣味や特技の欄がある場合は、できるだけ埋めておきましょう。
記入できる欄に空欄が多いと「誠実に就職活動に向き合っていない」、さらには「採用してもすぐに辞めてしまうのではないか」との印象を採用担当者に対して与えかねません。
ロースクール出身者は、ロースクール時代と学部生時代の両方の成績表を用意しておきましょう。
大学が遠方にある場合、成績表を郵送してもらう必要もあるため、その日数を踏まえた上で早めに大学側に連絡しましょう。
弁護士の履歴書はどのように記載する?
次に履歴書の書き方について解説します。
とくに志望動機の書き方で悩む人は少なくありませんが、志望動機以外にも重要なポイントがあります。
履歴書を作成する上で、まず意識すべきことは以下の3点です。
ゴールを設定する
何となく履歴書を書き始めて、必要事項を埋めていくのではなく、何を目指すのかを決めてください。
ゴールは採用担当者に「会いたい」「面接したい」「話を聞きたい」と思ってもらうことです。
そのために、どういう書き方がよいのか、どのような内容が適切なのかを整理しましょう。
丁寧に仕上げる
履歴書はパソコンで作成しましょう。(応募先から指定がある場合のみ手書きで作成)
印刷物を送付する場合はExcelやWordで作成したものをそのまま印刷しても問題ありませんが、メールや応募フォーム等からファイルを直接送付する場合はPDFに変換してから送付しましょう。
分量はA4サイズで1枚(多くても2枚)程度にまとめましょう。
大切なのは丁寧さ、見やすさです。空欄が目立ったり、内容を詰め込み過ぎていたりすると印象が悪くなります。
採用側のニーズを理解して自己PRする
履歴書を作成する前に、弁護士事務所・企業がどのような人材を求めているのか、採用ニーズを把握しましょう。
近年は募集条件、必須要件(歓迎要件)、適している人材、募集背景など求人票・求人ページで詳しく記載されているケースが増えています。
今までのキャリアや経験、興味のある分野と照らし合わせて、先方が興味をもてるように情報をまとめてください。
以上を踏まえた上で、履歴書内の項目ごとのポイントを説明します。
「志望動機」のポイント
志望動機でも最も大切なのは、「なぜ応募したのか」が明確に伝わる文章にすることです。
弁護士の就職先は数多くあります。
志望動機を作るコツは2つあります。
1つ目は、なぜ弁護士を目指したのか、どのような弁護士になりたいのか、どういうキャリアプランをもっているのか、どの分野や業務に強くなりたいのかなど、自分の軸をはっきりさせてください。
次に、それを実現できる職場である理由を整理します。事業内容や専門分野、過去の事例、理念など、あなたの軸に合う要素と結びつけます。
さらに、実際にどのような貢献をしたいのかが説明できれば、評価につながるでしょう。
「自己PR」のポイント
自己PRを書く際のポイントとして、以下の3点が挙げられます。
自分の性格・特徴を端的に表現する
自身の性格・特徴を述べる場合、弁護士としてのポテンシャルを感じさせる内容にすることが望ましいです。
たとえば、努力家である、素直である、物事に主体的に取り組める、などです。
一方、優しい、面倒見が良いといった内容は、人としては好ましい性格でも、弁護士という専門職の分野で活躍を期待できるかどうかという点ではあまり参考になりません。
弁護士業務に直結しない性格を強調しても、評価にはつながらないでしょう。
上記の具体的なエピソードを添える
これらの主張をするに当たって、必須となるのが根拠です。
自分や家族・友人など周りの人の主観的な評価ではなく、客観的評価(数値データ、実際にあったでき事、取得資格など)を根拠とします。
たとえば、自分が努力家であることを示したいなら、「小中高と野球に取り組み続けて、レギュラーになれなくても練習を休まなかった」「下級生にレギュラーの座を取られることもあったが、それでも諦めずに練習に打ち込んだ」などの例があると、説得力が高まります。
性格・特徴の根拠となるエピソードは、司法試験関連から選ばない方が得策です。
「司法試験合格を諦めなかった」といった話は、個人としては思い入れのある内容かもしれません。
しかし、ライバルとなる他の応募者も司法試験合格者であることから、採用する側である法律事務所・企業の法務部に属する人からすると希少性を感じずらい内容になりがちです。
どのような点で貢献できるかを記載する
自己PRは、自分の強みが伝わる内容にするのが基本ですが、ポイントは応募先の法律事務所・企業において活かせるもの、発揮できるものかどうかです。
どのようなすごいスキルや経歴、資格でも、就職後に活用できなければ評価対象とはなりません。
事務所・企業が求める人物像
弁護士として就職活動する際に評価されやすい人物像としては、以下が挙げられます。
コミュニケーション能力がある
弁護士業務では、クライアントに対応したり、法律事務所・企業法務部内のスタッフと意思疎通を図ったりと、日常的に人とコミュニケーションを取ることが不可欠です。
また、自分の意見を相手にきちんと伝達する能力、意見の異なる相手を説得できる論理的能力、同僚と協力して課題に取り組める協調性なども重要視されます。
リーダーシップがある・行動力がある
チームで案件に取り組む場合に、責任を負える覚悟をもてるかどうか、自分の意見を押し通さずにメンバーの意見を取り入れて行動できるかどうかは重要な資質です。
また、物事に対して受け身になるのではなく、自分から積極性をもって動けることも、弁護士業務を行う上では求められます。
明るい
ビジネスにおいても明るい性格の人は、人間関係を円滑に保ちやすく、フットワークが軽くてアクティブに行動できるイメージをもたれやすいです。
また、精神的にも強く、大きな壁にぶつかったときも、最後まで仕事をやり抜く力をもつとの評価を受けやすい傾向があります。
成長意欲を感じる
弁護士としての勤務未経験の人を採用する場合、参照できる実績がないため、採用の際に重視されるのはその人のポテンシャルや将来性、つまり「伸びしろ」を感じさせる人であるかどうかです。
そのように採用担当者に感じてもらうには、成長意欲を意図的にアピールする必要があります。学び続けたい、スキルを磨きたいなど、今後向上が期待できる姿勢をみせましょう。
考える力がある・思慮分別を感じさせる
弁護士にとって、論理的思考ができるかどうかは不可欠な資質です。
司法試験の論文試験を突破し、弁護士として就職活動をしようとしている時点で、考える力・思慮分別は十分にもっているといえます。
しかし、重要なのは、面接時の会話・受け答えの中でも同様の論理性を発揮できるかどうかです。
緊張しているとはいえ、話しているうちに矛盾した発言をしたり、根拠のないことを述べたり、論点からずれた発言をしたりすると、採用担当者から資質面で疑問をもたれてしまいます。
忍耐力がある
弁護士の仕事にはストレスがつきものです。
ノーストレスで快適に弁護士業務をこなしている人は、ゼロといっても過言ではないでしょう。
ストレスに耐えられず、自暴自棄になるような人、すぐに感情的になって周りの人を困らせてしまう人は、採用担当者によって適性を欠くと判断されます。
事務所に対して貢献する意識がある
面接の際に気を付けたいのは、「この事務所・企業であれば、~のような経験やスキルを身に付けられる」といった文言を多用してしまうことです。
しかし、応募者が殺到しているような事務所・企業の場合はとくにそうですが、採用担当者が注目しているのは「この人は事務所・企業に対してどのような貢献をしてくれるのか」といった視点です。
新人として就職活動をしているため、少しでも多くの経験をして、実績を積み上げたいと思うのは当然といえます。
しかし、自分が獲得したいこと・身に付けたいことばかり主張しても、採用する側としては採用する理由がありません。
「私には~のような強みや特徴があり、就職後に御事務所・御社に対して~のような貢献ができると思います」といった文言を提出書類や面接の場で使うようにすると、好印象をもたれやすいです。
面接で質問されること
法律事務所の面接でよく質問されること、およびその答えを見てみましょう。
弁護士を目指したきっかけ
「弁護士を目指したきっかけ」については面接の冒頭に聞かれることが多いです。
ただし、この質問は面接の緊張をほぐすアイスブレーキングが目的の可能性が高いため、過度に回答に慎重になる必要はありません。
「困っている人を助けたい」、「手に職を付けて知識や専門性を活かす仕事がしたい」、「大学で法律を学ぶ中で、興味をもった」などさまざまでしょう。
志望動機
志望動機は、面接でされる質問の中で最も重要となり、必ず質問されることになりますので、しっかりと準備しておきましょう。
志望動機を質問する意図は、大きく分けて2点です。
- ・事務所に対する興味や熱意の高さを推し量る
- ・事務所の取り扱い分野や雰囲気、条件とマッチするかを知りたい(ミスマッチを避けたい)
志望動機を記載する際は、事前にその事務所について調べること、自分の転職の軸を理解することが必要です。
Webサイトや代表弁護士の経歴など、インターネットで事前調査を行い、そこで得た内容から興味がもてるポイントを洗い出しましょう。
さらに求人票を確認し、「自分がその事務所にマッチしている理由」および「どのような貢献ができるのか」を、自分の経験や勉強・職務内容を紹介しながらしっかりと説明しましょう。
志望動機に対する答えは、単に「自分自身がなぜ志望したか」を説明するだけでは足りません。相手の立場に立って「自分がその事務所で貢献できる理由」までをアピールすることが大切です。
退職理由
弁護士になる前の職務経歴がある場合には「退職理由」も聞かれることになります。
退職理由を質問する目的は「応募者がすぐに辞めてしまわずしっかりと仕事をしてくれるか」を確認することが大きいです。
退職理由に対する答えは、人間関係など、どこの職場にもある事情については避けた方がよいでしょう。
また、前向きな印象を残すような答え方をすることも大きなポイントとなってきます。
どのような弁護士になりたいか
「どのような弁護士になりたいか」との質問は、応募者のキャリアプランと自分の事務所がマッチするかを確認するために行われることが一般的です。
たとえば、独立・転職のリスクがどの程度あるのか、あるいは全国展開する事務所なら「支店長」を希望するのかなどです。
ただし、どのような弁護士になりたいかは人それぞれだといえます。 自分のプランや思いを率直に答えましょう。
逆質問で聞くと良いことと悪いこと
面接の最後に「何か質問はありますか」と聞かれる、いわゆる「逆質問」は、必ず行った方がよいです。
逆質問をしない場合は「自分の事務所に興味がないのか」と見られてしまうこともあるからです。
ただし、場当たり的に、無理に質問を絞り出すことは逆効果です。
面接のやり取りの中で、聞きたかったことが答えられてしまうケースもあるため、事前に多めに質問事項を洗い出しておきましょう。
理想的には、「仕事に対する熱意を示せるようなもの」をするのがよいでしょう。
事件処理の進め方や大まかな仕事内容、クライアントの規模などについて質問される方は多いです。
報酬や勤務時間、休日などについても質問して構いません。ただし、諸条件の質問ばかりになってしまうと、仕事に対する熱意を疑われることになりかねないため、他の質問と織り交ぜるとよいでしょう。
また、事務所のWebサイトで確認できるようなことを質問すると、事前の情報収集不足が露呈してしまう可能性があるため、注意が必要です。
まとめ
弁護士として初めての就職活動を行う場合、アピールできる経験・実績がないため、性格や人間性、ポテンシャルといった定性的な側面が評価対象になりやすいです。
これらは提出書類の書き方、面接時の対応の仕方によって、採用担当者に与えるイメージは大きく変わってきます。
準備不足だと自分の良さを分かってもらえず、「本当の自分はこんな人間なのに」と思いながら不採用の通知を受け取ることになりかねません。
「弁護士という特殊な専門職ではどのような採用が行われるのか」について事前に内容を把握し、対策を練っておきましょう。
- #弁護士就活
- #弁護士就活スケジュール
- #弁護士就活時期


この記事を監修したキャリアアドバイザー

大学卒業後、ウェディングプランナー、業界大手で求人広告の企画提案営業を経て、MS-Japanへ入社。
企業担当のリクルーティングアドバイザーを経験した後、現在は転職を考えられている方のキャリアアドバイザーとして、若手ポテンシャル層~シニアベテラン層まで多くの方の転職活動のサポートをしています。
人材業界での経験も長くなり、いつまでも誰かの記憶に残る仕事をしていたいと思っています。
経理・財務 ・ 人事・総務 ・ 法務 ・ 経営企画・内部監査 ・ 会計事務所・監査法人 ・ 役員・その他 ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事

三大国家資格とは?試験内容と難易度、五大国家資格についても解説

行政書士は企業法務に転職できない?資格の活かし方や求人例など
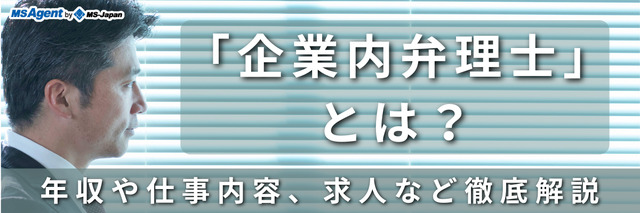
「企業内弁理士」とは?年収や仕事内容、求人など徹底解説

未経験でも転職はできる?MS-Japanの転職支援サービスを紹介!

検事のキャリア・仕事内容・給与やその後のキャリアパスについて
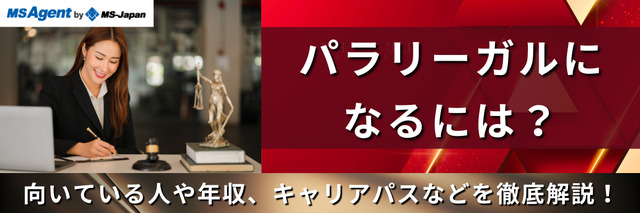
パラリーガルになるには?向いている人や年収、キャリアパスなどを徹底解説!

プライバシー侵害の判断基準とは?

後を絶たない業務上横領罪...... 中小企業で深刻化?

「みなし公務員」とは?一歩間違えれば贈収賄の可能性も!?
サイトメニュー


業界最大級の求人数・転職支援実績!管理部門・士業の転職に精通した専門アドバイザーがキャリア相談~入社までサポートいたします。
新着記事
求人を職種から探す
求人を地域から探す
セミナー・個別相談会


業界最大級の求人数・転職支援実績!管理部門・士業の転職に精通した専門アドバイザーがキャリア相談~入社までサポートいたします。