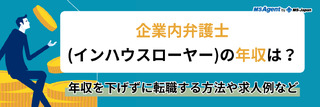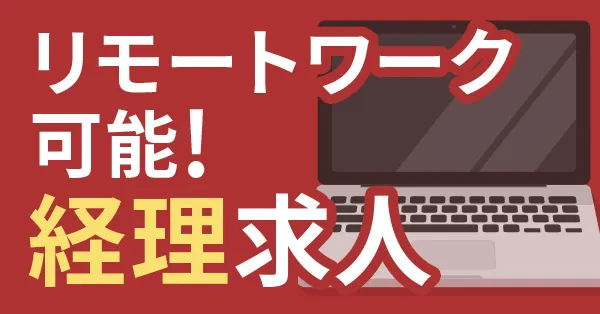弁護士の年収は意外と低い?平均年収や年収アップのポイントを紹介!
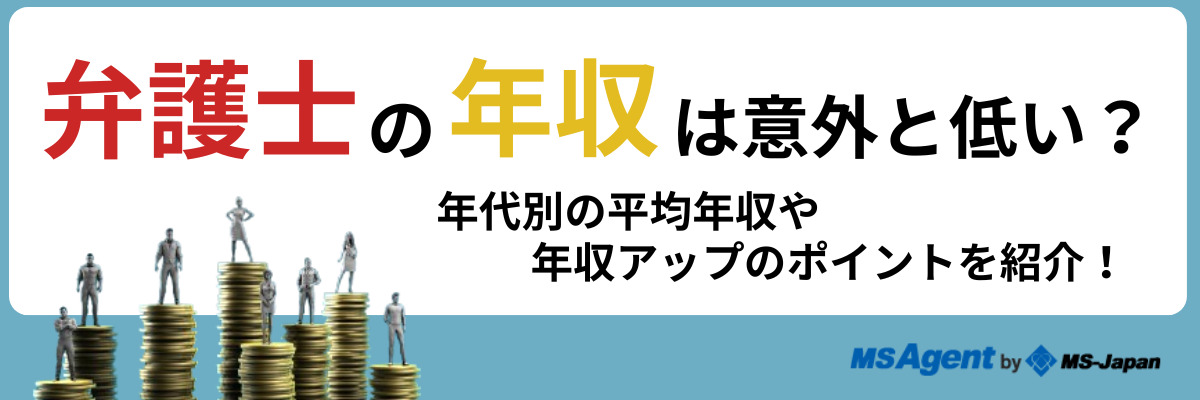
年収1,000万円以上の弁護士求人を探す
弁護士は、社会的な地位や専門性を持つことから、高年収が期待される職業です。
この記事では、弁護士白書のデータを基に、弁護士の平均年収を紹介します。
また、年収アップを目指す弁護士の方々に向けて、高年収求人の事例や転職成功事例を交えながら、年収を上げるためのポイントを解説します。
弁護士の平均年収
弁護士の平均年収については、日本弁護士連合会が発行する「弁護士白書」や、厚生労働省が発表する「賃金構造基本統計調査」など、さまざまな統計にて公表されています。
ただし、各統計によって母集団が異なるため、得られる年収データには違いがあります。
そこで本章では、複数の統計データをもとに、弁護士の年収傾向について紹介します。
弁護士の収入・所得|弁護士白書2023
まずは、日本弁護士連合会が発行する「弁護士白書 2023年版」による弁護士の収入と所得を紹介します。
ここで紹介するデータの母集団となる弁護士は、開業弁護士、勤務弁護士、組織内弁護士、官公庁に勤務する弁護士など、さまざまな就業形態の弁護士が含まれています。
| 収入と所得の 平均値・中央値 |
収入 | 所得 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,082.6万円 | 1,022.3万円 |
| 中央値 | 1,500万円 | 800万円 |
| 収入・所得の 分布割合 |
収入の割合 | 所得の割合 |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 2.1% | 10.0% |
| 200 万円以上 500万円未満 |
6.2% | 17.6% |
| 500 万円以上 750万円未満 |
11.7% | 19.0% |
| 750 万円以上 1,000万円未満 |
10.5% | 13.4% |
| 1,000 万円以上 1,500万円未満 |
16.9% | 15.9% |
| 1,500 万円以上 2,000万円未満 |
12.3% | 10.1% |
| 2,000 万円以上 3,000万円未満 |
17.0% | 6.6% |
| 3,000 万円以上 5,000万円未満 |
13.2% | 4.7% |
| 5,000 万円以上 7,500万円未満 |
5.1% | 1.2% |
| 7,500 万円以上 1億円未満 |
1.9% | 0.4% |
| 1億円以上 | 3.0% | 1.0% |
※「収入」とは、弁護士が仕事を通じて得る総収入のことを指します。一方、「所得」とは、収入から必要経費やその他の控除を差し引いた後に手元に残る金額を意味します。
収入と所得の両方を確認することで、弁護士としての実質的な経済状況を把握することができます。
上記のデータを見てわかるように、弁護士の年収には大きな幅があり、収入の格差が顕著です。
特に、収入が200万円未満の弁護士もいる一方で、1億円を超える高収入を得ている弁護士もいます。
この幅広い収入の差は、弁護士のキャリアや就業形態、専門分野によって大きく異なることを示しています。
また、収入と所得には大きな差が見られます。たとえば、収入の平均は2,000万円を超えていますが、所得は約1,000万円と大きく減少しています。
このことから、多くの弁護士がフリーランスや個人事業主として活動しており、収入から経費が差し引かれることで所得が減少していると考えられます。
年次別弁護士の収入・所得|弁護士白書2023
より詳しく確認するために、同じく2023年版の弁護士白書から、弁護士の経験年数ごとの収入・所得についても見ていきましょう。
| 経験年数 | 平均収入 (中央値) |
平均所得 (中央値) |
|---|---|---|
| 5年未満 | 575万円 (550万円) |
351万円 (300万円) |
| 5年以上10年未満 | 1,252万円 (1,027万円) |
685万円 (650万円) |
| 10年以上15年未満 | 1,975万円 (1,800万円) |
989万円 (860万円) |
| 15年以上20年未満 | 2,554万円 (2,100万円) |
1,252万円 (1,100万円) |
| 20年以上25年未満 | 3,763万円 (2,950万円) |
1,692万円 (1,215万円) |
| 25年以上30年未満 | 3,220万円 (2,680万円) |
1,298万円 (1,000万円) |
| 30年以上35年未満 | 2,687万円 (2,200万円) |
908万円 (695万円) |
| 35年以上 | 1,937万円 (1,300万円) |
734万円 (459万円) |
弁護士としての経験が浅い5年未満の層では、平均収入は575万円、所得は351万円と、弁護士全体の平均に比べて低いですが、5年以上になると大幅に増加します。
特に20年以上25年未満の弁護士では、平均収入が3,763万円とピークに達しています。
一方、30年以上のベテラン層では収入・所得がやや減少します。
このように、弁護士の収入はキャリアの途中でピークを迎え、その後は減少傾向にあることがわかります。
弁護士の平均年収|令和5年度賃金構造基本統計調査
次に厚生労働省が発表している「令和5年度賃金構造基本統計調査」による弁護士の平均年収を確認しましょう。
この調査によると、弁護士が含まれる区分「法務従事者」の年収(企業規模計10人以上)は約1,122万円です。内訳は以下の通りです。
| きまって支給する 現金給与額(月額) |
年間賞与その他 特別給与額 |
|
|---|---|---|
| 金額 | 77.8万円 | 196.72万円 |
ただし、「法務従事者」には弁護士以外の職種も含まれており、法律事務所に勤務する弁護士が業務委託契約を結んでいるケースも多いため、弁護士だけの平均年収としては正確ではありません。
データを総合すると、弁護士の年収は勤務形態やキャリアの進展によって大きく異なることがわかります。
特に開業弁護士やフリーランス弁護士では、収入の幅が非常に大きい一方、事業会社や法律事務所に勤務する弁護士は、比較的安定した年収を得られる傾向にあります。
【勤務先別】弁護士の平均年収
弁護士の年収は勤務先によって大きく異なります。
法律事務所に勤務する弁護士と、事業会社に勤務する弁護士(インハウスローヤー)の年収について、詳しく見ていきましょう。
法律事務所に勤務する弁護士の平均年収
法律事務所の規模は様々で、大手・準大手や中堅、ブティックファームなどによって事情は異なりますが、この章では大きく2つ、大手法律事務所と中小法律事務所に分けて、それぞれのケースについてご紹介します。
大手法律事務所
四大法律事務所のような大手法律事務所では、弁護士の役職が「ジュニアアソシエイト→シニアアソシエイト→パートナー」の順で昇進します(パートナーの中でも細かく段階が分けられている場合もあります)。
それぞれの役職ごとの年収は以下の通りです。
| 弁護士の役職 | 年収 |
|---|---|
| パートナー | 数千万円~数億円 |
| シニアアソシエイト | 1,600~3,000万円 |
| ジュニアアソシエイト | 1,100~1,500万円 |
1年目から年収1,000万円以上が見込めるのは、大手法律事務所のアドバンテージです。ただし、その分だけ業務量や質も高水準となるため、決して油断はできません。
中小法律事務所
中小法律事務所では、賃金制度や事務所の規模により年収が大きく変わります。
中堅クラスの事務所では700万円から800万円の年収が見込めますが、小規模な事務所では300万円からスタートすることもあります。
また、地方よりも東京などの都市部で勤務する弁護士の方が、年収が高くなる傾向にあります。
キャリアや専門分野を活かして、特化型の事務所を選び、年収を上げることも可能です。
事業会社に勤務する弁護士(インハウスローヤー)の平均年収
企業法務(インハウスローヤー)は、法律事務所で勤めたり開業したりする場合に比べて、一般的には年収が低いといわれています。
しかし、ワークライフバランスや福利厚生面の充実という観点から見ると、プライベートな時間が確保しやすいなどのメリットもあります。
働いている企業の給与体系にもよりますが、日本組織内弁護士協会が2023年3月に実施した「企業内弁護士によるアンケート調査集計結果」を見る限り、インハウスローヤーの半数以上が500万円以上1,250万円未満の年収をもらっているようです。
250万円以上500万円未満の年収となっている弁護士は、わずか2.9%と少数派であり、ほとんどの弁護士は一般的な給与所得者に比べれば高い給料をもらっているものと考えてよいでしょう。
弁護士の高年収求人例(年収1,000万円以上)
ここでは、弊社MS-Japanで扱う弁護士の高年収求人例をご紹介します。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
シニアアソシエイト弁護士/企業法務系事務所
| 仕事内容 |
|
・企業法務 ・一般個人法務 ・プロボノ活動 |
| 必要な経験・能力 |
|
・弁護士資格者(目安5年目以降) ・ビジネスレベルの語学力 |
| 想定年収 |
| 1,000万円~1,500万円 |
企業内弁護士
| 仕事内容 |
|
・法務相談対応 ・訴訟法務対応 ・訴状、申立書の作成、手続き |
| 必要な経験・能力 |
| ・弁護士資格保有者 |
| 想定年収 |
| 1,000万円~1,800万円 |
法務・リスクマネジメント責任者/IPO準備企業
| 仕事内容 |
|
・法的側面からの事業戦略策定への関与 ・契約書作成、レビュー、交渉 ・会社運営全般に際しての機関法務業務 |
| 必要な経験・能力 |
|
・2年以上の法務経験 ・弁護士資格 |
| 想定年収 |
| 1,000万円~1,800万円 |
年収1,000万円以上の弁護士求人を探す
弁護士の年収で知っておくべき3つの特徴
弁護士は、実力や当人の希望次第で、働き方や勤務先を自由に選べます。
以下、弁護士の給与体系の特徴をご紹介します。
年齢の上昇に従って年収が増える傾向にある
弁護士の年収は、年齢とともに増える傾向があり、60代以降になっても高年収が得られる職種の一つです。
これは、弁護士を頼るクライアントが、その弁護士の経験・実績を重視していることに理由があるものと推察されます。
弁護士になりたての若年者は、どうしても経験・実績に乏しく、就職先もある程度限定されてしまいます。
そのため、キャリアをスタートさせた段階では、どうしても高年収を実現できる例は少なくなります。
努力次第で生涯年収は青天井
若年者の年収が決して高くない傾向にあるとはいえ、年齢の上昇に従って年収が増えること自体は、弁護士のアドバンテージといえます。
なぜなら、一般企業で定年まで勤め上げる状況を想定した場合、50代になってから役職定年がスタートして給料が減少し、そこから定年・再雇用という流れでさらに給料は少なくなり、年齢とともに給料は下がってしまうのが普通だからです。
大手弁護士事務所でパートナーを目指すにせよ、独立して自力で案件を獲得するにせよ、弁護士は努力次第で生涯年収が増えていく職種です。
弁護士は、年を重ねるごとに経験・実績が重宝されるため、給料も青天井といえるでしょう。
収入格差はある
稼げる弁護士がいる一方で、世の中のニーズをつかめなかったり、世間から十分な評価を得られなかったりする弁護士も少なからず存在しています。
弁護士数が増えたのに案件が変わらないということは、需要量よりも供給量が増えていることを意味しますから、弁護士の給料にも収入格差が生まれてしまうのは避けられません。
弁護士は、業歴が古いほどしっかりとした顧客基盤を築きやすく、弁護士になったばかりで独立してもなかなか集客が難しいのが現実です。
かといって、地方の法律事務所や小規模な事務所で働くだけでは、なかなか年収・給料も伸びません。
とはいえ、弁護士の活躍のフィールドは伝統的な訴訟等の交渉業務から、企業法務まで幅広く、インハウス弁護士という選択肢も一般的になってきていますので、年収をアップさせるためには、弁護士としての専門性以外にも、自らの能力・適性を正確に把握しておく必要があります。
弁護士として年収を上げる方法とは?
独立をすれば自分の力で高年収を目指せる弁護士ですが、勤務弁護士として給料をもらう立場で年収アップを狙う場合、独立時のように多くの選択肢があるわけではありません。
組織の中で認められるよう、組織に「欲しがられる」能力を鍛えることが、弁護士として高年収を実現するためのポイントとなるでしょう。
ここでは、「専門性を身につける」「より条件の良い勤務先へ転職する」の2点を解説します。
専門性を身につける
まずは、専門性を身につけることです。
弁護士として特定の法律分野や業界の専門性を深くすることで、その分野のエキスパートとしての地位を築けます。
たとえば知的財産権、M&A、国際取引など、特定の領域での専門的な知識やスキルは高く評価され、それに伴い報酬も上がる傾向です。
一般的な法律分野よりも、競合が少ないニッチな分野を選択しつつその分野でのパイオニアとなることで、独自の価値を提供する方法もあります。
より条件の良い勤務先へ転職する
年収を上げる手っ取り早い方法は、より条件の良い勤務先へ転職することです。
一般的に、大手の法律事務所や外資系の法律事務所は、高額な報酬を提供しているケースが多く見られます。
大規模な案件を取り扱う機会が増え、それに伴い年収も上昇する傾向があります。
転職を通して年収を上げるには、先ほど紹介した専門性の獲得や、入念な企業研究が重要です。
転職を考える際には、弁護士の転職に強い転職エージェントを利用することで、自身のスキルや経験を最大限に活かせる勤務先を見つけやすくなります。
管理部門・士業特化の転職エージェント「MS Agent」では、業界に精通したキャリアアドバイザーがあなたの転職活動をお手伝いします。
「MS Agentって他のエージェントと何が違うの?」と疑問に思われた方は、
完全無料の転職サポート「MS Agent」のメリットをご確認ください。
年収アップに成功した弁護士の転職事例をご紹介!
40代弁護士の転職成功事例

Aさん(40代/男性)
プライム上場メーカー
年収:1,000万円


プライム上場メーカー
年収:1,200万円
Aさんは上場企業の法務部長として経験を積んでいましたが、会社の業績が芳しくなく、多くの同僚が退職している状態でした。
Aさん自身も現状に不安を感じており、親しかった同期が退職したことをきっかけに転職活動を開始しています。
Aさんがとくに注力したのは、「自己分析」「企業研究」の2つです。
各企業の研究では、面接前にコンサルタントから情報を集め、面接での質問を予想して準備を行いました。
さらに前職での経験を活かし、同じ業界(メーカー)の求人を選んでいるのも重要なポイントです。
Aさんは、前職での経験と姿勢が評価され、年収200万円アップの1,200万円での採用内定を得ています。
30代弁護士の転職成功事例

Bさん(30代/男性)
大手建築不動産企業
年収:650万円


非上場中堅の建築不動産企業
年収:800万円
Bさんは、法律事務所での経験をもち、東証プライム上場の大手建築不動産企業で活躍していました。
家庭の事情でBさんが一人で家計を支える必要が生じ、それがきっかけで転職を決意しています。
Bさんは、自身の希望に合う求人が見つかるまで転職活動を続け、同業界の求人を中心に検討しました。
最終的には、規模が一段小さい同業界の企業に、ポジションをアップして転職しています。
金融機関から外資系法律事務所への転職成功事例

Cさん(30代/男性)
大手金融機関
年収:800万円


外資系法律事務所
年収:1,000万円
Cさんは司法修習中に弁護士事務所ではなくインハウスを選択し、当事者としての経験を積むことを重視していました。
次第に「法律事務所でより専門性を深めて活躍したい」というキャリアプランをもつようになり、インハウスローヤーとして金融機関での経験を活かし、グローバルに活躍することを目指すようになったそうです。
Cさんは金融機関の経験を最大限に活かし、外資系法律事務所を希望していました。
転職活動では外資系法律事務所をターゲットに絞り込み、各ファームの企業分析に注力していたそうです。
結果として、当初の希望通り、外資系法律事務所から内定を受け取りました。
明確なキャリアプランとターゲットの絞り込み、そして専門性の追求が転職成功の鍵であることがわかります。
年収だけじゃない!弁護士の魅力とは
さまざまな人と関わることができる
弁護士は、日常的にクライアント、裁判官、検察官、他の弁護士など、さまざまな背景をもつ人々と接触します。
人間関係のスキルを磨きつつ、多様な視点や考え方を学べるのは、まさに弁護士ならではの魅力でしょう。
弁護士は、多岐にわたる分野での問題を取り扱います。
これによりさまざまな業界の専門家や関係者との交流が生まれるのも重要なポイントです。
たとえば、企業の問題を取り扱う際には、経営者や会計士、税理士との連携が必要となるケースがあります。
パズルを解くような面白さがある
クライアントから持ち込まれる問題や事件は、多くの場合、複雑で多面的です。
解決するためには、事実関係を整理し、関連する法律や判例を適用する必要があります。
こうしたプロセスは、パズルのピースを正しい位置に配置するような作業と似ています。
さらに弁護士は、裁判や交渉の際に、相手方の動きや意図を予測し、最も有利な結果を得るための戦略を立てる必要があり、戦略的な思考を多く必要とされる部分に、魅力を感じる人も多いのではないでしょうか。
働き方が比較的自由に選べる
弁護士は、資格をもっていれば自らの事務所を開設し、独立して業務を行えます。
企業に勤めるのとは異なり、自分のペースやスタイルで仕事をすることが可能です。
また、独立開業することで、自分の得意分野や興味をもつ分野に特化した業務を選択できます。
たとえば現代のテクノロジーの進化により、弁護士もリモートワークを選択することが増えてきました。
自宅や好きな場所での業務が可能となり、働き方の選択肢が広がっています。
固定の勤務時間が設定されていないため、自分のライフスタイルや家庭の状況に合わせて働く時間を調整しやすいのも魅力的です。
弁護士×年収に関するよくある質問
Q.法律事務所から事業会社へ転職する場合は年収が下がりますか?
A.一般的には、法律事務所の方が年収が高い傾向にあるため、事業会社へ転職する際に年収が下がるケースが多いです。
しかし、近年では事業会社における弁護士の需要が増加しており、特に企業が必要とする専門領域での経験を持っている弁護士は、事業会社でも高い年収を得られる場合があります。
さらに、事業会社では福利厚生が充実していることが多く、年収以外の待遇面で法律事務所よりも良い条件を提示されることが少なくありません。
したがって、全体的な待遇を考慮すると、転職後の生活の質が向上することもあります。
事業会社の中でも弁護士の年収が高い業界はどこですか?
事業会社の中で弁護士の年収が高い業界としては、大手金融機関、大手総合商社、大手マスコミなどが挙げられます。
これらの業界では、法務部門が重要な役割を果たしており、複雑な法律問題を扱うことが多いため、弁護士に対して高い報酬が支払われることが一般的です。
また、国際取引やM&A(企業の合併・買収)に関わることが多い業界でも、弁護士の年収が高くなる傾向があります。
まとめ
いくつかの転職事例からもわかるように、弁護士でも転職を通して年収アップが期待できます。
明確なキャリアプランを用意しつつ、現職で専門性を獲得することで、転職活動もスムーズに進めやすくなるでしょう。
転職では、自己分析や企業研究など、やるべきことが多くあります。
自分の力だけでは難しいと感じたら、転職エージェントのサポートを得るのがおすすめです。
MS Agentでは、専門のアドバイザーが当事者の悩みに合わせたサポートを提供しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
管理部門・士業特化の転職エージェント「MS Agent」では、業界に精通したキャリアアドバイザーがあなたらしい転職をお手伝いします。
「MS Agentではどのようなサポートをしてくれるの?」と疑問に思われた方は、 「MS Agent」の転職サービス紹介をご確認ください。
- #弁護士の年収
- #高年収ランキング

 求人特集
求人特集年収1,000万円以上の弁護士求人を探す
この記事を監修したキャリアアドバイザー

大学卒業後、ウェディングプランナー、業界大手で求人広告の企画提案営業を経て、MS-Japanへ入社。
企業担当のリクルーティングアドバイザーを経験した後、現在は転職を考えられている方のキャリアアドバイザーとして、若手ポテンシャル層~シニアベテラン層まで多くの方の転職活動のサポートをしています。
人材業界での経験も長くなり、いつまでも誰かの記憶に残る仕事をしていたいと思っています。
経理・財務 ・ 人事・総務 ・ 法務 ・ 経営企画・内部監査 ・ 会計事務所・監査法人 ・ 役員・その他 ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事

三大国家資格とは?試験内容と難易度、五大国家資格についても解説

行政書士は企業法務に転職できない?資格の活かし方や求人例など
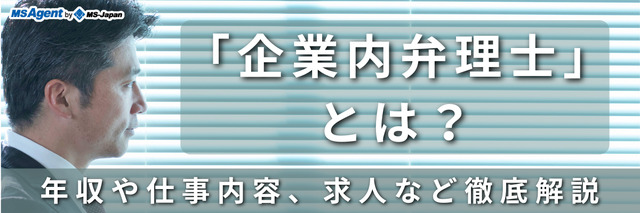
「企業内弁理士」とは?年収や仕事内容、求人など徹底解説

未経験でも転職はできる?MS-Japanの転職支援サービスを紹介!

検事のキャリア・仕事内容・給与やその後のキャリアパスについて
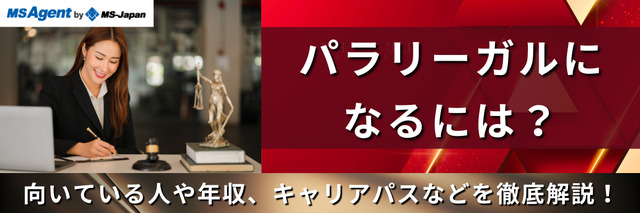
パラリーガルになるには?向いている人や年収、キャリアパスなどを徹底解説!

プライバシー侵害の判断基準とは?

後を絶たない業務上横領罪...... 中小企業で深刻化?

「みなし公務員」とは?一歩間違えれば贈収賄の可能性も!?
サイトメニュー


業界最大級の求人数・転職支援実績!管理部門・士業の転職に精通した専門アドバイザーがキャリア相談~入社までサポートいたします。
新着記事
求人を職種から探す
求人を地域から探す
セミナー・個別相談会


業界最大級の求人数・転職支援実績!管理部門・士業の転職に精通した専門アドバイザーがキャリア相談~入社までサポートいたします。