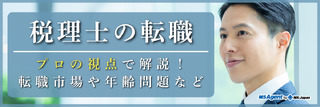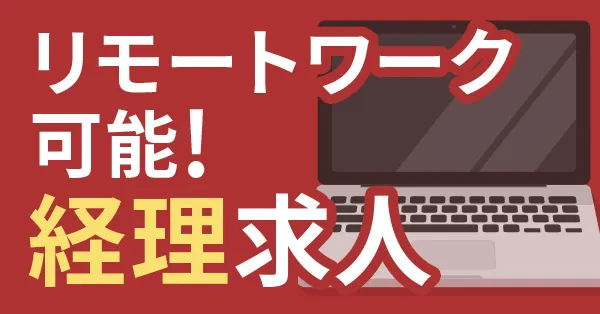独立したい税理士必見!開業後の年収や働き方、”段階的な独立準備”とは?

独立支援制度あり事務所の求人を探す
税理士としてのキャリアを歩むなかで、「いつかは独立したい」と考える税理士の方は少なくありません。
自らの力で顧客を獲得し、収入や働き方を自由に設計する。そうした理想を実現している独立税理士も実際に存在します。
しかし一方で、準備不足のまま独立開業に踏み切り、事業継続が困難になるケースも少なくありません。
この記事では、税理士の独立を現実的に成功させるための判断軸とステップを、士業に特化した転職エージェントの視点から徹底解説します。
この記事で分かること
・税理士が独立するうえで理解しておくべきメリット・デメリット
・税理士の独立は何歳、何年目が目安なのか
・営業活動や資金面に不安がある方におすすめの「段階的な独立」とは
税理士が独立するメリット・デメリット
税理士が独立することには、メリットとデメリットの両面があります。
キャリアに正解はありませんが、独立を検討する際には、これらを正しく理解しておくことが重要です。
税理士が独立するメリット
独立のメリットは主に「収入の上限がないこと」「裁量の広さ」「仕事のやりがい」の3点に集約されます。
収入に上限がない
独立を目指す税理士にとって、最も大きな魅力は、収入に上限がないことです。
勤務税理士の年収相場は、年齢や勤務先の規模によって異なりますが、一般的には約800万円とされています。
一方で、独立して成功している開業税理士は、年収1,000万円を超えるケースも珍しくなく、努力とスキル次第で年収2,000万、3,000万円も目指すことが可能です。
もちろん、クライアントの獲得や価値のあるサービス提供といった努力は必要ですが、勤務時代の年収を大きく上回ることも十分可能です。
自由度のある働き方
案件の選び方やスケジュールを自分で調整できるため、家族との時間を重視したライフスタイルを築ける点も独立の魅力です。
働く場所も自由に選べるため、通勤によるストレスがなくなり、結果として業務効率の向上も期待できます。
専門性を活かせる
得意分野に特化したい方にとっても、独立は大きなチャンスとなります。
勤務時代は事務所の方針に従う必要がありましたが、独立すれば、自分の専門分野に特化したサービスを展開できます。
相続税対策、医療機関支援、DX導入支援など、専門性を打ち出すことで競合との差別化が図れます。
税理士が独立するデメリット
独立する場合の主なデメリットは、「収入の不安定さ」と「業務に対する責任の重さ」に集約されます。
収入や将来への不安
独立に不安を感じる方の多くは、安定した収入を得られない可能性を懸念しています。
2024年の帝国データバンクの調査によれば、税理士事務所の休廃業・解散率は5.61%で、全業種の中で最も高い水準となっています。
独立開業しても、クライアントを十分に確保できなければ、安定した収入は望めません。
また、社会保障や福利厚生がなくなることも将来的な不安要素です。
勤務時代には会社が半額を負担していた社会保険料も、独立後はすべて自己負担となります。
退職金や有給休暇といった福利厚生も受けられなくなるため、将来に向けた備えは自身で行う必要があります。
参考:全国企業「休廃業・解散」動向調査2024|帝国データバンク
仕事への責任の重さ
税理士が独立すると、税務業務に加えて営業活動や事務所の経営まで、自ら幅広い業務を担う必要があります。
クライアントに対する業務責任に加え、経営方針の決定や資金繰りなど、経営者としての判断も求められます。
経営判断の誤りがそのまま収入の減少に直結するため、常に高い緊張感と責任を持って意思決定を行う必要があります。
税理士として独立すべきか、判断のポイント
独立に向いている人の特徴
税理士として独立に向いている人の特徴には、いくつかの共通点があります。
1つ目は、自己管理能力と主体性がある人です。
自由な働き方は独立の大きな魅力ですが、その分、自律的に継続して働く姿勢が求められます。
誰かの指示を待つのではなく、自ら課題を発見し、解決に向けて考え、実行に移す積極性が必要です。
2つ目は、営業力がある人です。
税務知識や実務スキルがいかに優れていても、独立後に顧客を獲得できなければ事業は成り立ちません。
勤務時代は、事務所や企業が仕事を与えてくれますが、独立後はプレゼンテーション能力やコミュニケーション力、人脈構築力を活かして、自ら案件を獲得していく必要があります。
あわせて読みたい
勤務税理士がおすすめな人の特徴
一方で、安定志向の方や税務業務に専念したい方には、勤務税理士としてのキャリアがおすすめです。
大手や準大手の税理士法人では、専門性を追求できる環境が整っており、収入や福利厚生も比較的充実しています。
近年は働き方改革の進展により、税理士法人や会計事務所でも労働環境が改善されており、独立しなくてもワークライフバランスを重視した働き方が可能になっています。
「安定を重視したいが、収入も上げたい」「プライベートの時間も大切にしたい」といった方は、無理に独立を選ぶ必要はありません。
自分に合った働き方ができる職場を探してみるのも、有効な選択肢の一つです。
独立までの3つのステップ
税理士が独立開業を成功させるには、事前準備を十分に行うことが不可欠です。
ここでは、独立までの流れを簡単に紹介します。
STEP1:開業資金を準備する
税理士事務所を開業するには、一定の資金が必要です。
開業資金は、自宅開業でも50万円程度、自宅とは別に事務所を構える場合では約200万円の初期費用が必要となります。
また、クライアントがいる状態での開業でない場合は、開業後2〜3か月は収入が不安定になる可能性があります。
そのため、生活費を含めた運転資金もあわせて確保しておきましょう。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」など、公的な融資制度の活用も検討が必要です。
STEP2:登録・開業手続きを行う
税理士が個人事業主として開業する場合は、税務署への「開業届出書」や「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
あわせて、事務所の住所や屋号の決定、業務に必要な備品の準備など、実務面の体制も整えていきます。
STEP3:集客・営業の準備を始める
開業後に安定して顧客を確保するには、事前の集客体制の準備が極めて重要です。
ホームページやSNSでの情報発信を通じて専門性をアピールし、問い合わせにつなげましょう。
勤務時代に築いた人脈や紹介ルートを活かせる環境に身を置いておくことも、開業直後の安定に直結します。
あわせて読みたい
税理士の独立は何歳・何年目がベスト?
税理士は、登録までに時間がかかることや一定の実務経験で科目免除があることから、平均年齢が高い傾向があります。
そうした背景もあり、独立を目指すタイミングとしては「税理士登録から5〜10年程度の実務経験を積んだ30代後半〜40代前半」が一つの目安となります。
5〜10年程度の実務経験があれば、幅広い税務業務経験に加えて、顧客からの信頼も得られる時期のため、独立後も比較的スムーズに事業を立ち上げやすいとされています。
とはいえ、20代や50代で独立する事例もあり、年齢による制限があるわけではありません。
結局のところ、「何歳で独立すべきか」に正解はなく、重要なのは十分な準備と戦略をもって独立に踏み出せるかどうかという点です。
独立税理士の年収は高い?
独立税理士の年収実態
勤務税理士の平均年収は、事務所や企業の規模や地域にもよりますが、一般的には約800万円とされています。
一方、開業税理士の年収は事務所規模やクライアント数によって大きく異なります。
なかには、年収1,000万円を超えるケースも珍しくありません。
ただし、開業1年目の年収は300〜400万円程度からスタートすることが多く、勤務時代を下回る場合も少なくありません。
順調にクライアントを獲得できれば、3〜5年目で勤務時代の年収を上回ることも十分に見込めます。
年収アップを実現するポイント
営業・マーケティング力で安定収入を築く
どれだけ専門性が高くても、顧客にその価値が伝わらなければ、ビジネスとしては成立しません。
独立後は自ら営業・発信する力が不可欠です。
近年は、ブログやSNS、YouTubeなどを活用して、認知度向上や専門性の発信に取組む税理士が増えています。
さらに、専門分野や業界に特化することで、ブランディングによる差別化も実現できます。
付加価値のあるサービスで単価を上げる
現在では、記帳代行や税務申告といった基本的な税務サービスは競合が多く、価格競争が激化しています。
特にオンライン完結型や低価格路線の事務所が増えており、単価を維持しにくい状況です。
そのため、年収を向上させるためには、高付加価値なサービスを提供することが重要です。
たとえば、経営コンサルティングや事業計画策定支援、資金調達サポート、事業承継対策など、クライアントの経営課題に踏み込んだサービスを展開することで、価格競争に巻き込まれず、高い報酬を得ることができます。
業務効率化で利益率を高める
クラウド会計ソフトやAI-OCRなどのITツールを導入することで、記帳や書類作成といった定型業務の効率化が可能になります。
また、必要に応じて事務スタッフやアシスタントを雇い、自分は高付加価値業務に集中する体制を構築すれば、時間あたりの利益を最大化できます。
効率的な業務フローを整備することで、少ないリソースでも安定的な収益基盤を築くことが可能です。
いきなり独立は危険?「段階的な準備」という選択肢
独立を目指す税理士にとって、「今すぐ独立するか、それとも十分な経験を積んでからにするか」は重要な判断ポイントです。
営業や資金面への不安から、独立に踏み切れない税理士も少なくありません。
準備不足での開業は、リスクが大きいのが現実です。
こうした不安を抱える方におすすめしたいのが、「段階的に独立を目指す」というアプローチが有効です。
独立支援制度を設けている会計事務所では、開業を前提とした実務経験を積みながら、段階的に準備を進められます。
具体的な支援内容は事務所によって異なりますが、以下のような制度が整備されているケースがあります。
- ・顧客紹介制度:初期顧客の獲得をサポート
- ・開業支援:資金調達やオフィス開設に関するノウハウを提供
- ・ノウハウ共有:営業・経営の実務スキルを実践的に習得
- ・のれん分け制度:既存顧客の引き継ぎによるスムーズな開業
これらの制度を活用すれば、独立に伴う不安やリスクを最小限に抑えながら、経営者としての実力を確実に養うことが可能です。
管理部門・士業に特化した転職エージェント「MS-Japan」では、将来の独立を支援している税理士法人や会計事務所の求人情報も取り扱っています。
独立支援制度の詳細や過去の独立実績、現在働いている税理士の声など、独立を目指す税理士にとって重要な情報を事前に確認できるため、自分に適した環境を選択できます。
まずは無料の会員登録をして、独立支援制度のある会計事務所を比較検討することから始めてみるのも一つの方法です。
独立支援制度のある会計事務所求人
ここでは、独立支援制度のある会計事務所の求人を紹介します。
MS-Japanでは、業界最大級の求人数の中から、ご自身の希望に合う求人のご紹介が可能です。
税務シニアコンサルタント|独立歓迎の会計事務所
| POINT |
|
・将来に独立を考えている方歓迎 ・専門分野を身に着けられる環境◎ ・在宅勤務・時短勤務可能 ・パートナーは世界四大会計事務所出身 |
| 仕事内容 |
| ・税務業務全般 ・事業承継・資産承継サポート ・各種税務コンサルティング業務 |
| 想定年収 |
| 500万円~800万円 |
契約社員|中小企業の経営支援に強い税理士法人
| POINT |
|
・独立志向の方も歓迎 ・中小企業経営に関して幅広い経験が積める環境 ・独自の成長考課制度 |
| 仕事内容 |
|
・月次/年次決算 ・経営分析資料作成 ・納税支援および税務届出 |
| 想定年収 |
| 600万円~1,200万円 |
独立支援制度あり事務所の求人を探す
税理士の独立を取り巻く現状と将来性
税理士の独立開業については、「厳しい」「生計を立てにくい」といった否定的な意見も散見されます。
このようなネガティブなイメージが広がっている背景には、以下のような業界動向があります。
- ・税理士は増えているのに顧客となる企業は減っている
- ・会計ソフトが税理士の仕事を奪っている
- ・税理士は定年がないためベテランが多い
- ・公認会計士などに仕事を取られている
それぞれの理由について詳しく解説します。
税理士登録者数が増えている
税理士の独立後の厳しさの一因として、税理士登録数の増加が挙げられます。
日本税理士連合会の調べによると、税理士の登録数は以下の表の通り、右肩上がりで増え続けています。
| 年度 | 税理士登録者数 |
|---|---|
| 令和元年度 | 78,795人 |
| 令和2年度 | 79,404人 |
| 令和3年度 | 80,163人 |
| 令和4年度 | 80,692人 |
| 令和5年度 | 81,280人 |
| 令和6年度 | 81,696人 |
| 令和7年度 | 81,493人 (令和7年5月末日現在) |
直近5年間でも2,000人以上増加しており、その傾向は今後も続く見込みです。
今後も税理士が増え続けることで、将来的に税理士業界が飽和状態となる可能性もあるでしょう。
会計ソフト・AIが税理士の仕事を奪っている
近年、ほとんどの企業で「クラウド会計ソフト」が導入されています。
クラウド会計ソフトは、税務の素人でも日常の経理業務や税金の申告を簡単にできるほどの利便性を備えています。
また、入力作業や計算、定型的な書類作成業務などはAI化されていく可能性が高いでしょう。
従来は税理士の業務であった中小企業の経理業務・税務申告がクラウド会計ソフトやAIに置き換わることにより、従来税理士が担っていた業務の一部が代替されつつあると指摘されています。
あわせて読みたい
開業税理士は定年がないためベテランが多い
開業税理士には定年はありません。
そのため、ベテランの税理士は意欲がある限りずっと働き続けます。
長年培った豊富な経験やスキルがあり、新規の顧客を獲得しやすいベテラン税理士が引き続き活躍することで、新規参入した若い税理士が顧客を獲得しにくい状況が生まれているとも言われています。
弁護士や公認会計士などに仕事を取られている
税理士登録をしている人のなかには、弁護士や公認会計士も多くいます。
弁護士や公認会計士は、それぞれの資格と組み合わせて税務の業務を行うために、より広い範囲の業務を受注することができます。
その結果、税理士の資格のみで業務を行う開業税理士が仕事を取られていると言われています。
FAQ|税理士の独立に関するよくある質問
Q.税理士が独立するまで何年かかりますか?
税理士試験合格から独立までには、通常7〜12年ほどかかるケースが一般的です。
税理士登録に必要な2年の実務経験に加え、幅広い税務や営業スキルを身につけるため、5〜10年程度の勤務経験を経て独立するのが一般的です。
Q.独立して最初の顧客はどうやって見つけますか?
多くの税理士が、勤務時代の人脈や知人からの紹介で最初の顧客を獲得しています。
ホームページやSNSでの情報発信、セミナーの開催、紹介サイトへの登録なども効果的です。
重要なのは開業前からの準備です。
Q.独立して後悔する人もいますか?
営業への苦手意識や収入の不安定さ、孤独感などから、独立後に困難を感じるケースもあります。
準備不足により収入が伸び悩み、精神的に追い込まれるケースもあります。
そうしたリスクを避けるためにも、独立前に現実的な計画を立て、最悪のケースを想定した対策を講じておくことが重要です。
Q.人脈がない場合でも独立は可能ですか?
人脈がなくても独立は可能ですが、集客に時間と労力がかかります。
ホームページ、SNS、セミナー、異業種交流会などを活用して認知度を高めましょう。
継続的な情報発信を通じて、自身の専門性をアピールし、顧客からの信頼を着実に築いていくことが重要です。
まとめ
税理士としての独立は、収入や働き方の自由といった大きな魅力がある一方で、リスクも伴う慎重な判断が求められる選択です。
収入や働き方の自由、専門性を活かしたサービス展開などは独立ならではの醍醐味ですが、その裏には収入の不安定さや経営責任といった現実も存在します。
だからこそ重要なのは、理想だけでなく、自身の経験やライフプランを踏まえて、「今、本当に独立すべきか」を冷静に見極めることです。
独立はキャリアの通過点であり、人生を左右する一手でもあります。
準備を十分に行い、適切なタイミングと手段を選択できれば、自身にとって最適なキャリア形成が可能になるでしょう。
もし、「段階的に独立を目指したい」「独立に向けた環境で力を試してみたい」と感じている方は、MS-Japanの転職支援サービスをぜひご活用ください。
独立支援制度のある会計事務所の紹介から、将来を見据えたキャリア形成のご相談まで、幅広くサポートしています。
- #税理士
- #税理士独立
- #独立開業

 求人特集
求人特集独立支援制度あり事務所の求人を探す
この記事を監修したキャリアアドバイザー

大学卒業後、大手サービス会社にて法人営業を経験、その後人材紹介会社にてキャリアアドバイザー経験を経て、MS-Japanへ入社。
主に会計事務所、弁護士事務所の担当を持ちながら士業領域での転職を検討している方のカウンセリングから案件紹介を担当。
会計事務所・監査法人 ・ 法律・特許事務所 ・ 税理士 ・ 税理士科目合格 ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事

会計事務所が求める人材とは│事務所規模ごとに解説

未経験でも転職はできる?MS-Japanの転職支援サービスを紹介!

会計事務所が使用するソフトウエアとは?シェア状況を公開
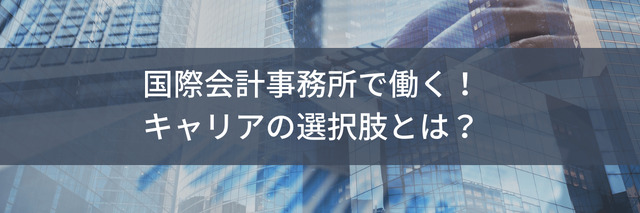
国際会計事務所で働く!キャリアの選択肢とは?
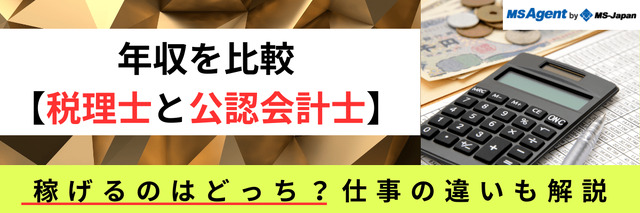
年収を比較【税理士と公認会計士】稼げるのはどっち?仕事の違いも解説

≪財務コンサル業界≫ ブティック型のコンサルって何?

会計事務所にお勤めの方へ 人事評価や転職で評価される資格とは?

在宅勤務可能な会計事務所が増加中!税理士・会計士のテレワーク事情

税理士から公認会計士にキャリアチェンジするべきか?業務や年収の違いは?