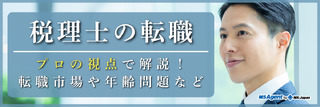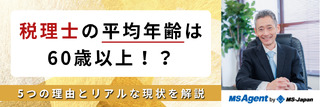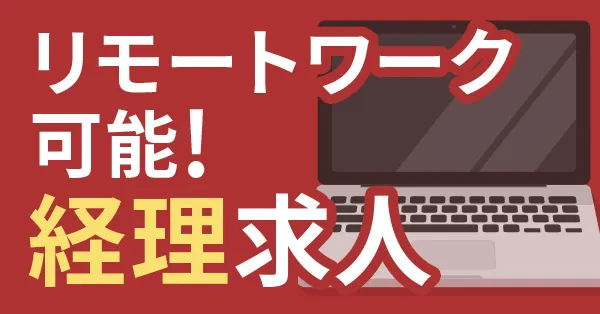【解説】税理士試験とは?科目別合格率と難易度、おすすめの科目など

税理士試験勉強応援中の
会計事務所求人を探す
税理士資格は、「税務書類の作成」「税務代理」「税務相談」の3つの独占業務を持ち、転職や独立といった場面でも有利に働く国家資格です。
税理士試験の受験を検討する中で、「どのくらい難しいのか」「どの科目を選ぶべきか」といった点が気になる方も多いでしょう。
本記事では、税理士試験の基本情報や仕組み、受験科目の選び方、取得後のキャリアについて分かりやすく解説します。
税理士試験とは?
税理士試験とは、税務に関する国家資格である「税理士資格」を取得するための試験で、「会計学に属する科目」と「税法に属する科目」に分かれています。
資格取得のためには、合計5科目の合格が必要ですが、科目合格制度が採用されており、5科目すべてを一度に合格する必要はありません。
合格した科目の有効期限はなく、生涯にわたって保持されます。また受験の回数制限もありません。
そのため、多くの税理士試験受験者は、毎年1~2科目を受験しながら数年をかけて5科目合格を目指します。
税理士試験の試験科目
税理士試験は、必修科目、選択必修科目および選択科目全11科目の中から、合計5科目の合格が必要です。
税理士試験の試験科目を見ていきましょう。
必修科目(2科目)
会計学に属する「簿記論」「財務諸表論」の2科目は、全員が合格必須です。
選択必修科目(1科目以上)
税法に属する「所得税法」「法人税法」から、少なくとも1科目を選択し、合格する必要があります。なお、両方の科目に合格することも可能です。
選択科目(必修・選択必修と合わせて合計5科目になるように選択)
以下の科目から、選択必修科目で選択した数に応じて1科目または2科目を選択します。
・相続税法
・消費税法 または 酒税法(いずれか一方)
・国税徴収法
・住民税 または 事業税(いずれか一方)
・固定資産税
例えば、「選択必修科目」を1科目(例:法人税法)選択した場合は、「選択科目」から2科目を選択します。
一方、「選択必修科目」を2科目とも選択した場合は、「選択科目」からは1科目を選択すれば合格要件を満たします。
受験料
受験料は、受験を申し込む科目数に応じて以下の通りです。
| 科目数 | 受験手数料 |
|---|---|
| 1科目 | 4,000円 |
| 2科目 | 5,500円 |
| 3科目 | 7,000円 |
| 4科目 | 8,500円 |
| 5科目 | 10,000円 |
※令和7年度(2025年度)試験時点となります。
受験地
税理士試験の受験地は、以下のうちから希望のものを選択します。
ただし、受験者数などの状況に応じて変更になることがあります。
北海道・宮城県・埼玉県・東京都・石川県・愛知県・大阪府・広島県・香川県・福岡県・熊本県・沖縄県
税理士試験の受験資格
税理士試験は、会計学に属する2科目は誰でも受験が可能ですが、税法に属する科目には受験資格が設定されています。
税法に属する科目の受験資格は「学識」「資格」「職歴」の3種類に分かれており、いずれか1つに当てはまることが必要です。
学識
・大学、短大または高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
・大学3年次以上の学生で社会科学に属する科目を含めて62単位以上を取得した者
・特定の専修学校の専門課程を修了した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
・司法試験合格者
・公認会計士試験短答式試験合格者(平成18年度以降の合格者に限る。)
資格
・日商簿記検定1級合格者
・全経簿記能力検定上級合格者
職歴
・法人または事業を営む個人の会計に関する事務に通算2年以上従事した者
・税理士、弁護士、公認会計士などの補助事務に通算2年以上従事した者
・銀行、信託会社、保険会社などにおいて、資金の貸付け・運用に関する事務に通算2年以上従事した者
※参考: 国税庁「税理士試験受験資格の概要」
令和8年度(2026年)の税理士試験日程
税理士試験は、例年8月上旬の3日間で実施されます。
令和8年度の試験日程は以下のとおりです。
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 試験実施官報公告 | 令和8年4月3日 |
| 受験申込受付 | 令和8年4月20日 |
| 受験申込受付締切 | 令和8年5月8日 |
| 試験実施 | 令和8年8月4日~ |
| 合格発表 | 令和8年11月27日 |
なお、日程については変更される可能性があります。国税庁の公告はまめに確認しましょう。
※参考: 国税庁「令和8年度(第76回)税理士試験実施スケジュールについて(予定)」
税理士試験と日商簿記の比較
税理士試験の試験科目である「簿記論」は、出題範囲が日商簿記検定と重なるため、まず簿記検定を受験し、その後に税理士試験を目指すケースが一般的です。
また、日商簿記1級は税理士試験の受験資格でもあるため、他の受験資格を満たしていない場合は、日商簿記1級を取得することをおすすめします。
日商簿記1級は難易度が高いため、保有することで転職や就職活動において評価されやすくなります。
あわせて読みたい
【科目別】税理士試験の受験者数・合格者数・合格率
税理士試験の令和7年度における受験者数・合格者数・合格率を、試験科目ごとにご紹介します。
| 科目 | 令和7年度 受験者数 |
令和7年度 合格者数 |
令和7年度 合格率 |
[参考] 令和6年度 合格率 |
前年との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簿記論 | 18,466人 | 2,058人 | 11.1% | 17.4% | -6.3% |
| 財務諸表論 | 15,629人 | 4,980人 | 31.9% | 8.0% | 23.9% |
| 所得税法 | 1,120人 | 146人 | 13.0% | 12.6% | 0.4% |
| 法人税法 | 3,606人 | 488人 | 13.5% | 16.4% | -2.9% |
| 相続税法 | 2,413人 | 333人 | 13.8% | 18.7% | -4.9% |
| 消費税法 | 7,064人 | 712人 | 10.1% | 10.3% | -0.2% |
| 酒税法 | 590人 | 72人 | 12.2% | 12.1% | 0.1% |
| 国税徴収法 | 1,671人 | 231人 | 13.8% | 13.0% | 0.8% |
| 住民税 | 439人 | 78人 | 17.8% | 18.2% | -0.4% |
| 事業税 | 310人 | 38人 | 12.3% | 13.7% | -1.4% |
| 固定資産税 | 928人 | 144人 | 15.5% | 18.0% | -2.5% |
| 合計 | 52,236人 | 9,280人 | 17.8% | 13.5% | 4.3% |
※参考: 国税庁「令和7年度(第75回)税理士試験結果(科目別)」
【科目別】税理士試験の難易度・合格までに要する学習時間目安
税理士試験の科目別勉強時間は、一般的に以下の表のように言われています。
| 科目名 | 平均勉強時間(目安) |
|---|---|
| 簿記論 | 400~500時間 |
| 財務諸表論 | 400~500時間 |
| 所得税法 | 600~700時間 |
| 法人税法 | 600~700時間 |
| 相続税法 | 400~500時間 |
| 消費税法 | 300時間 |
| 酒税法 | 150時間 |
| 国税徴収法 | 150時間 |
| 住民税 | 200時間 |
| 事業税 | 200時間 |
| 固定資産税 | 250時間 |
選択科目や必須科目は、1年に1科目ずつ合格できれば、順調なペースといえます。
ただし、簿記論と財務諸表論は同時に学習し、1年で2科目受験する人も少なくありません。
税理士試験は計算問題と理論問題で構成されますが、簿記論は計算問題のみの構成です。
計算と理論をバランスよく学習するためにも、簿記論だけを学習するのではなく、財務諸表論と合わせて学習する方が多いと考えられます。
転職で評価されやすい税理士試験科目とは?
税理士試験の科目選択では、単に合格しやすいかどうかだけでなく、その後のキャリアにどう活かせるかも重要な判断基準となります。
ここでは、転職時に評価されやすい科目を紹介します。
実務での使用頻度が高い5科目
簿記論
企業活動における取引の記録方法を扱う科目で、会計の基礎となる知識が問われます。
税務申告書作成の前提として、正確な帳簿作成能力は不可欠であり、ほぼすべての会計事務所で求められるため、評価されやすい科目です。
財務諸表論
財務諸表の作成や分析に関する理論的な理解を問う科目で、決算書の構造や開示の根拠となる考え方を学びます。
実務では決算対応や税務申告に直結する知識として重視されており、評価されやすい基本科目です。
法人税法
法人税は国税収入額の中でも2番目に多く、ほぼすべての会計事務所で扱われるため、実務での使用頻度が高く、評価されやすい代表的な科目です。
所得税法
国税収入額トップであり、個人の一年間の所得に対して課される国税で、実務でも使われる大変重要な科目です。
消費税法
ほとんどの会計事務所業務では、必ずと言っていいほど消費税法を利用します。
消費税法は、法人・個人問わず幅広く関係するため、実務適用の幅が広く、評価されやすい科目です。
実務での評価が高まっている2科目
相続税
少子高齢化が進むことで、相続税関連業務も増加しています。
相続税に特化した事務所の需要が高まっており、一般的な会計事務所でも取り扱う機会が増えています。
固定資産税
相続関連業務のニーズの高まりに伴い、評価が高まってきた科目です。
不動産オーナーの相続や資産承継を扱う場面が増えており、固定資産税の専門知識が重視される傾向があります。
ミニ税法は実務での活用は限定的なことも
酒税法・国税徴収法・住民税・事業税などのミニ税法は、比較的学習量が少なく済むため科目合格のハードルは低い傾向があります。
一方で、実務での活用シーンは限られるため、転職時に高評価につながるケースは少ないでしょう。
【キャリア別】評価される税理士試験科目
税理士科目は、目指すキャリアによっておすすめの組み合わせや科目は異なります。
ここでは、転職先別に税理士科目の組み合わせをご紹介します。
法人向け会計事務所を目指す場合
日本企業の約99.7%が中小企業であり、会計事務所が主に支援する対象も中小企業が中心です。つまり、会計事務所にとって中小企業支援は最大のマーケットといえます。
中小企業支援には、「簿記論・財務諸表論」といった会計科目の基礎的な知識が必要です。
一方、上場企業を含む大企業向けの支援には、「法人税」の専門知識が求められます。
法人向けサービスを展開する会計事務所を目指す場合、「簿記論・財務諸表論・法人税法」がおすすめ科目といえるでしょう。
相続税特化型の会計事務所を目指す場合
近年、相続税のニーズが高まるにつれ、一般法人の支援をサービスとして取り扱わない相続税に特化した会計事務所の設立も増加しています。
このような特化型の事務所では、「相続税」または「固定資産税」の税理士試験科目合格者を積極的に採用する傾向があります。
税理士試験受験者を支援する会計事務所が増加
多くの受験者は毎年1〜2科目ずつ受験し、数年かけて5科目の合格を目指します。そのため、働きながら合格を目指す場合は、勉強時間の確保が重要な課題となります。
近年は、会計事務所の人材不足によって、税理士試験受験者を支援し、将来の人材確保を目指す事務所が増加しています。
試験当日の休暇はもちろん、試験前の残業削減や長期休暇の取得、自習スペースの設置など、各事務所で多様な支援が導入されています。
また、会計事務所で税理士補助として働きながら勉強に取り組むことで、実務を通じて税理士の働き方を間近で学べるだけでなく、税理士登録に必要な実務経験も同時に積むことができます。
税理士資格を取得するメリット・デメリット
ここでは、税理士資格を取得するメリット・デメリットをご紹介します。
税理士資格を取得するメリット
税理士資格を取得する主なメリットは以下の2つです。
独立開業が可能になる
税理士資格は、独立して自身の事務所を構えることができる数少ない国家資格のひとつです。
将来的に「自分の裁量で働きたい」「クライアントと直接関わりながら価値を提供したい」と考える方にとって、非常に大きな武器になります。
▶ 独立したい税理士必見!開業後の年収や働き方、”段階的な独立準備”とは?
年齢にとらわれず、生涯現役で働ける
税理士は、定年のない専門職です。会社勤めの場合は60歳前後で定年退職を迎えますが、税理士として開業すれば、体力や意欲が続く限り現役で活躍できます。
実際に、税理士の平均年齢は60歳を超えており、経験や人脈を活かして長く働いている方が多く存在します。
▶ 税理士の平均年齢は60歳以上!? 5つの理由とリアルな現状を解説
税理士資格を取得するデメリット
一方で、資格取得までには相応のハードルもあります。メリットだけでなく、以下の点も理解したうえで目指すことが大切です。
取得までに多くの時間と費用がかかる
税理士試験は長期戦になりやすく、合格までに数年を要するケースも珍しくありません。
特に働きながら合格を目指す方は、勉強時間を確保するだけでも大変です。
一般的に、全科目合格までには約4,000時間の学習が必要といわれており、資格学校や教材費なども含めると経済的負担も小さくありません。
まとめ
税理士は、税務の独占業務を持ち、独立開業や年齢にとらわれないキャリア形成が可能な、極めて専門性の高い国家資格です。
しかし、資格を取得するには、合計5科目に合格する必要があり、数年単位での計画的な学習と多大な努力が求められます。
本記事で解説したように、どの科目を選択するかは、単に合格のしやすさだけでなく、その後のキャリアを大きく左右する重要な戦略的判断となります。
働きながらの学習に課題を感じている方、または実務経験を積みながら効率的に合格を目指したい方は、受験生への支援制度が整った会計事務所への転職も有力な選択肢です。
自身のキャリアプランに合致した環境を選ぶことが、目標達成への近道となるでしょう。
士業・管理部門特化型転職エージェント「MS-Japan」は、あなたのキャリアプランに寄り添い、資格取得をサポートする優良な会計事務所の求人を多数ご用意しています。
多忙なあなたの転職活動を専任のキャリアアドバイザーが力強くサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
- #税理士試験
- #税理士科目
- #税理士試験 合格率

 求人特集
求人特集税理士試験勉強応援中の
会計事務所求人を探す
この記事を監修したキャリアアドバイザー

大学卒業後、大手出版系企業を経て現職へ入社。
主に大手・新興上場企業を対象とする法人営業職を4年、キャリアアドバイザーとして10年以上に及ぶ。
経理・財務 ・ 人事・総務 ・ 法務 ・ 経営企画・内部監査 ・ 会計事務所・監査法人 ・ コンサルティング ・ 役員・その他 ・ IPO ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!
 あなたへのおすすめ求人
あなたへのおすすめ求人
同じカテゴリの最新記事

会計事務所に就職・転職するには?事務所選びや年収アップのポイントなど

在宅で働く税理士が増えている!リモート可の会計事務所に転職するためのポイントや求人例を紹介!

税理士補助とは? 仕事内容や年収、求人情報、志望動機のポイントも解説

会計事務所が求める人材とは│事務所規模ごとに解説

会計事務所の転職理由【例文付】面接の注意点や失敗しない転職先選びのポイント
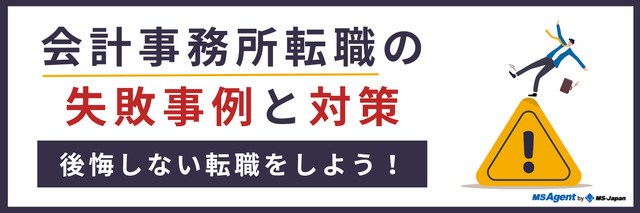
会計事務所転職の失敗事例と対策。後悔しない転職をしよう!
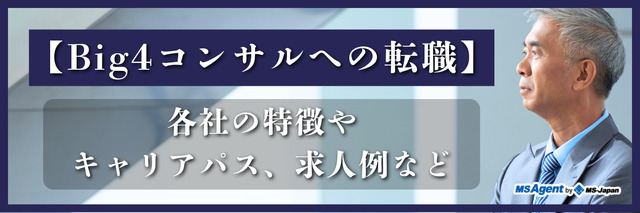
【Big4コンサルへの転職】各社の特徴やキャリアパス、求人例など

【職種別】会計事務所に向いている人とは?向いていない人の特徴も併せて解説
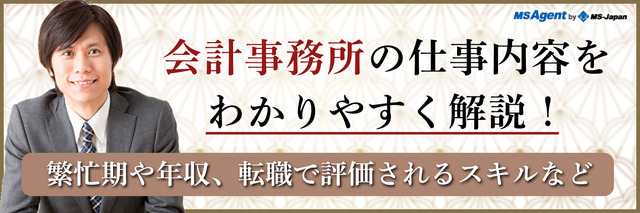
会計事務所の仕事内容をわかりやすく解説!繁忙期や年収、転職で評価されるスキルなど